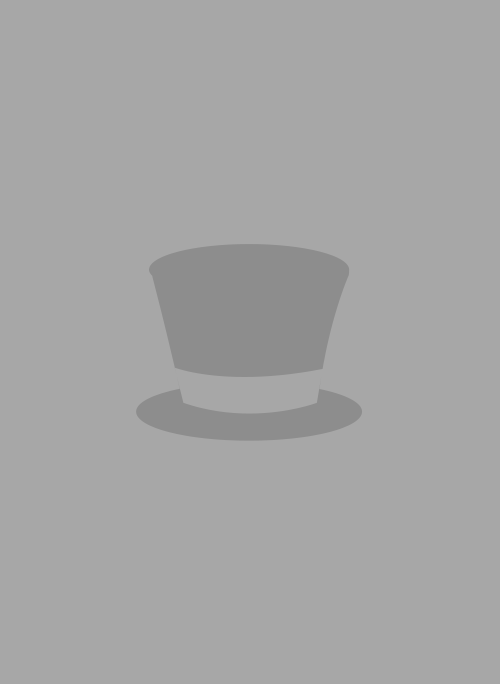翌日、アポイントも取らずに侘助の実家を尽は訪ねた。
緊張した面持ちで待つのは香の匂いのする応接室だ。
(お香の匂いがする…)
すんすんと鼻を鳴らす尽の背中から丸い声がする。
「どうかしたのかい?」
「いや…」
「で…今日は?」
尽の前のソファーに座る。
「先日、お借りした物を返しに来ました」
知新博物館の紙袋を見せる。
「綴は…仕事かい?」
「はい。暇なのは俺だけなんで来ちゃいました」
「じゃあ、アンタも博物館の?」
「そうです…アルバイトなんですけど」
「それで今日は学生服なのか?綴の友達にしては若すぎると思ったよ…で…アンタはなんだい?特技と言うか…変わった人が多いからね、あの博物館は」
笑顔を絶やさず侘助の祖母が問う。
「へぇ…アンタがねぇ…私なんかに話しても良かったのかい?」
尽は自分の能力を簡単に説明した。
「お祖母さんなら…だから…この部屋の香の匂いもきになってて…」
「ああ…これかい?隣の部屋で紙に香を移してるんだよ。扇子なんかの紙に使うんだ」
自分の胸元に差してあった扇子を手渡す。
「本当だ」
すんすんと鼻を鳴らす尽を侘助の祖母が見つめる。
「綴は…ちゃんとやってるんだね?」
「はい」
「そうかい…家を継ぐ気は無いんだろうね…アンタ…その鼻で分かったりしないのかい?」
「残念ながら…」
嫌味の無い祖母の言い口に顔を見合わせて笑う。
「まぁ…先が分かったら面白くないからね…」
お茶請けとして尽に勧めた麩まんじゅうと竹筒羊羹を土産に持たせてくれた。
「はい…」
「…綴は寄り付かないんだ…アンタがたまには顔を出しとくれ」
博物館に戻って来た尽は、率先して持たせて貰った菓子を修復室で広げる。
「あ…ここのお菓子美味しいですよね?私、お茶入れて来ます」
雨衣が気を使う様に部屋を出る。
「…何か言ってましたか?」
「俺の能力で侘助さんに家を継ぐ気があるか分からないか…って」
ふっ…と鼻で笑った侘助が言う。
「あの人らしい…先が分かったって楽しくないですからね…」
「それ…同じ事言ってました」
「私が…家を出る時に言った事なんですよ…そこには共感してくれたみたいで…でも、私は未来よりも古い事が知りたい…」
カタカタと近づいて来た茶碗の触れ合う音に気付いた侘助が雨衣の為にドアを開ける。
「雨衣と歩くの久しぶりだよね?」
すっかり侘助の花は落ち、緑が濃く見える正門までを歩く。
「うん。ねぇ…侘助さんのおばあちゃんと何話したの?」
「ああ…俺の能力の話。あの(知新)博物館は変わった人が多いから…って笑ってたけど」
「そこに私も含まれちゃうのかな?」
「雨衣は自分は普通だと思ってるの?」
「え?普通でしょ?なに?どうしたの?」
「自覚無し?」
「自覚?私はただのフォント・オタクって位で…」
「あ…ねぇ…雨衣の家はどんな感じ?」
覗き込んだ雨衣が狼狽える。
「どう…って…家も普通だと思うけど…それこそ、私の周りでは色んな事が起きてるから何が普通か…なんて考えた事がないけど」