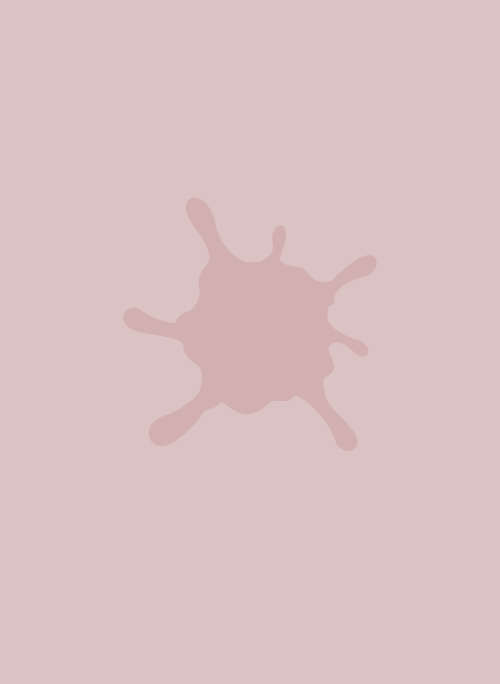そのとき、弱い風が吹き、彼女の髪の毛を撫でた。
彼女の髪の毛がゆっくりと舞う。
普通にしていたらいいのに、何でこんな冗談みたいな性格をしているんだろう。
「でも、半分は本気だったりするよ」
彼女は風の中に解けてしまいそうなほど、静かな声でそう囁いた。
「それって」
そのとき、靴箱が騒がしくなっていく。
もうすぐ昼休みも終わりなのだろう。
「戻ろうか。久司君」
そういって、彼女は笑顔を浮かべていた、
彼女の髪の毛がゆっくりと舞う。
普通にしていたらいいのに、何でこんな冗談みたいな性格をしているんだろう。
「でも、半分は本気だったりするよ」
彼女は風の中に解けてしまいそうなほど、静かな声でそう囁いた。
「それって」
そのとき、靴箱が騒がしくなっていく。
もうすぐ昼休みも終わりなのだろう。
「戻ろうか。久司君」
そういって、彼女は笑顔を浮かべていた、