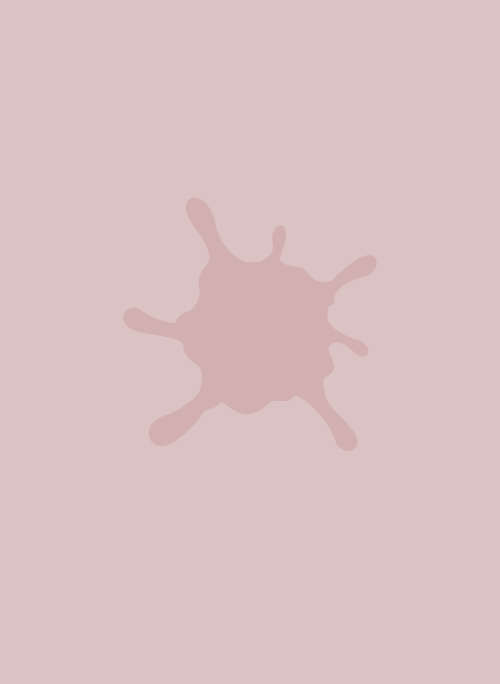「でも、心配だから」
彼女は顔を赤く染めると、うなずいていた。
「分かった。ありがとう」
まるで暗闇の中に存在感を示すかのように木々が色づいている。
僕の手に当たっていた風がさえぎられる。
彼女を見ると、彼女は優しく微笑んでいた。
「紅葉って素敵だね」
彼女は僕の手をつないだまま銀杏の葉を手に取ると、かざして見せた。
「そうだね」
その情景はやけに幻想的で、彼女と二人で別世界に迷い込んだようだった。
先ほどまで体を襲っていた風の強さも、冷たさも全く気にならなくなっていた。
まるで彼女の誕生日を祝うかのように用意された景色のように見えた。
そして、傍らにいる彼女のぬくもりをただ一緒に感じていたのだ。
彼女は顔を赤く染めると、うなずいていた。
「分かった。ありがとう」
まるで暗闇の中に存在感を示すかのように木々が色づいている。
僕の手に当たっていた風がさえぎられる。
彼女を見ると、彼女は優しく微笑んでいた。
「紅葉って素敵だね」
彼女は僕の手をつないだまま銀杏の葉を手に取ると、かざして見せた。
「そうだね」
その情景はやけに幻想的で、彼女と二人で別世界に迷い込んだようだった。
先ほどまで体を襲っていた風の強さも、冷たさも全く気にならなくなっていた。
まるで彼女の誕生日を祝うかのように用意された景色のように見えた。
そして、傍らにいる彼女のぬくもりをただ一緒に感じていたのだ。