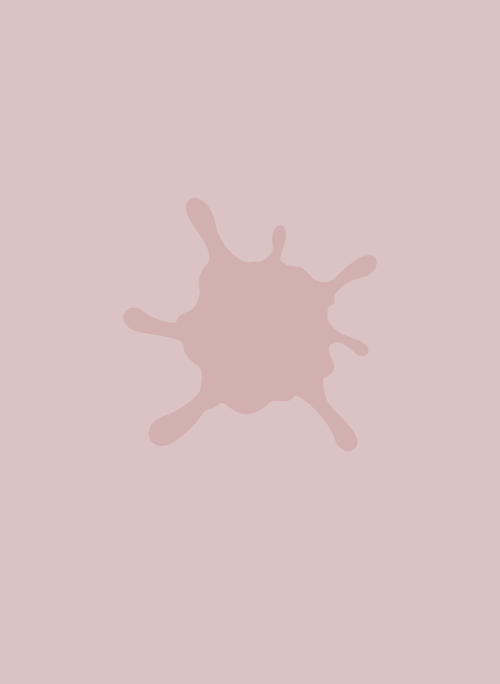「瀬戸口くん?」
「あのさ、間違ってたらあれなんだけど・・・。
吉野さんのストーカーってあの人?」
指を指された方を向くと、ちょうど黒いパーカーをかぶった男の人らしき人物が気づかれたと思い、逃げようとする最中のところだった。
「え・・・?」
待って。
私にストーカーなんていなかったはず。
きっとあの人は何かの間違いだよ。
うん、きっとそう・・・。
「なんだ、お前本当にストーカーに付け回されてたのか?」
私の小さな不安なんておかまいなしに水嶋が聞いてくる。
「知らない・・・。
そんなの私が聞きたいよ!」
あの人が私のストーカーと決まったわけじゃないのに、恐怖と不安が入り混じってパニックになる。
「どうしよう・・・」
明日もあの人がここにいたらどうしよう。
後なんて付けられたらどうしよう。
怖くてこの道を歩けないかもしれない。
「怖い・・・」
さっきまで私にストーカーなんて存在しないと思っていたのに、いざいるとなるとどうしていいのかわからない。
頭を抱えて思いを巡らせていると、温かいものがふわっと頭の上に置かれた。
「そんな怯えんなって。
俺たちがついてる」
あの作り笑顔でもでもなく、意地悪な不敵の笑でもなく、昨日の別れ際に見せた優しい表情で水嶋は私の頭を撫でていた。
「そうだよ。
吉野さんを守るために僕たちがいるんだからさ。
ちゃんと頼ってね?」
瀬戸口くんも笑顔で私に笑いかける。
きっと二人は私を安心させようとしてるんだ。
そう思うとほんのり胸が暖かくなって、喉がきゅっと熱くなり、今にも泣きそうになってしまう。
なんとか涙は我慢して、私は今二人に
「ありがとう・・・」
と伝えることでいっぱいいっぱいだった。
ありがとう。