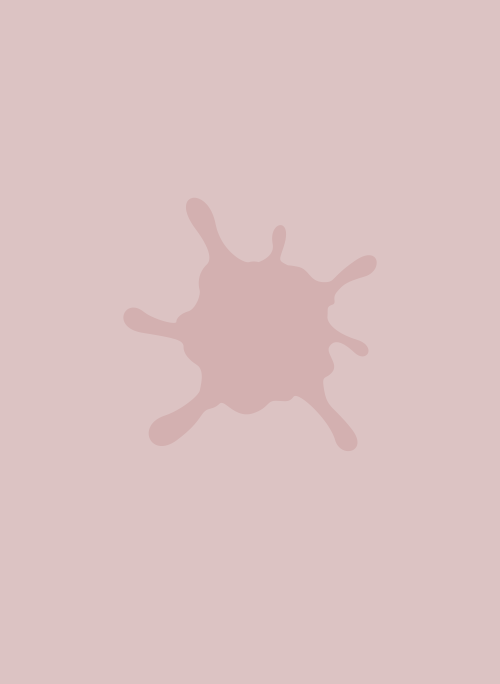「ごめんね、」
上から彼の泣きそうな声が聞こえてきて、俺は涙で腫れた顔をあげた。
すると、前に見た不細工すぎる笑みではなく今にも泣きそうに眉を寄せた雪村君と目が合う。
「ごめんね…。
ありがとう。少しでも、オレと友達になろうとしてくれて。でもやっぱり、」
雪村君は、ギュッと自分の学ランをつかみ、いつか見た寂しそうな笑みを浮かべた。
「やっぱり、わからないみたい。君の言う、『当然』が」
「あ……」
急に罪悪感に駆られて、俺は彼に謝ろうとした。
でも謝れば、自分の発言を否定することになる。
結局、俺はなにも言えなかった。