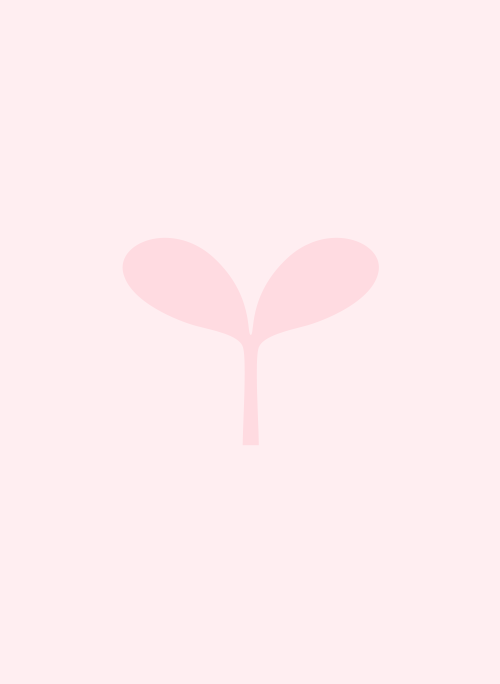「十兵衛殿」と声をかけられて振り返ると、見覚えのある侍が一人、人混みの中をこちらに歩み寄って来るところだった。
毎年、初夏の城下を賑わす蛍祭りは、この季節の夕べの風物詩である。
城下を流れる川の河原には大勢の人間が集まり、思い思いにか弱い光を放つ小さな虫を楽しんでいた。
もっとも、同じ河原でも
武士の身分の者が楽しむ場所と町人たちの楽しむ場所は橋をはさんで分けられており、私が今立っているのはちょうどその境界の──
つまり城下の大通りにかかる太鼓橋の下だった。
橋の下まで歩いてきた四十代半ばのその男は、独特のとろりとした双眸を私に向けた。
先法御三家の一つ、菊田家の今の当主──菊田水右衛門である。
最近、御用番の支配役に就いたと聞いている。
「お久しぶりです」と頭を下げる私に、優美な着流し姿でどこか退廃的に笑む水右衛門は、以前まみえた時の紅顔の美丈夫の面影を残してはいるものの、
やや白いものが混ざり始めた頭やたるみ始めた顔の輪郭が、流れた年月分の老いを感じさせた。
「早いものよな。あれからもう十余年か」
そう呟く男を見て、少し違うかと思った。
むしろこの男の場合は、若い頃から年に似合わず老成したような──
物事を達観し尽くしたような──
まるで老人のような空気を放っていた。
奇妙な老いを感じさせる男の内面に、ようやく実年齢が追いつき始めたと言うほうが正しいのかもしれない。
「ああ、今はもう──十兵衛殿は武士の身分を捨て、名も改められたのだったかな」
私はそう言われて、静かに頷く。
「今宵は蛍狩りで?」
「いえ、弔いに」
川の上や草の間で光っては消える小さな光を眺めながら、私がそう答えると、
水右衛門は何のことか理解した様子で「ああ」と頷いた。
「あの死んだ二人の……か」
「死んだ三人の、弔いです」
「三人? はて?」
毎年、初夏の城下を賑わす蛍祭りは、この季節の夕べの風物詩である。
城下を流れる川の河原には大勢の人間が集まり、思い思いにか弱い光を放つ小さな虫を楽しんでいた。
もっとも、同じ河原でも
武士の身分の者が楽しむ場所と町人たちの楽しむ場所は橋をはさんで分けられており、私が今立っているのはちょうどその境界の──
つまり城下の大通りにかかる太鼓橋の下だった。
橋の下まで歩いてきた四十代半ばのその男は、独特のとろりとした双眸を私に向けた。
先法御三家の一つ、菊田家の今の当主──菊田水右衛門である。
最近、御用番の支配役に就いたと聞いている。
「お久しぶりです」と頭を下げる私に、優美な着流し姿でどこか退廃的に笑む水右衛門は、以前まみえた時の紅顔の美丈夫の面影を残してはいるものの、
やや白いものが混ざり始めた頭やたるみ始めた顔の輪郭が、流れた年月分の老いを感じさせた。
「早いものよな。あれからもう十余年か」
そう呟く男を見て、少し違うかと思った。
むしろこの男の場合は、若い頃から年に似合わず老成したような──
物事を達観し尽くしたような──
まるで老人のような空気を放っていた。
奇妙な老いを感じさせる男の内面に、ようやく実年齢が追いつき始めたと言うほうが正しいのかもしれない。
「ああ、今はもう──十兵衛殿は武士の身分を捨て、名も改められたのだったかな」
私はそう言われて、静かに頷く。
「今宵は蛍狩りで?」
「いえ、弔いに」
川の上や草の間で光っては消える小さな光を眺めながら、私がそう答えると、
水右衛門は何のことか理解した様子で「ああ」と頷いた。
「あの死んだ二人の……か」
「死んだ三人の、弔いです」
「三人? はて?」