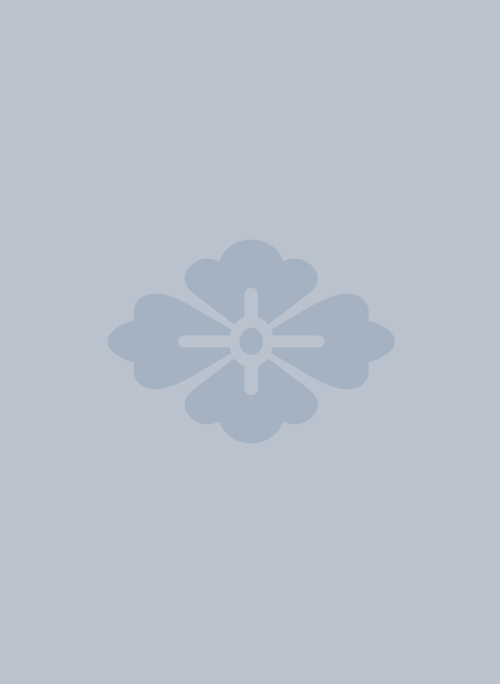「全く、酷い親だよ。最後くらい優しく嘘でもついてやればいいものを…」
先程お母と話していた女の人が呆れたようにあたしたち親子をみていた
「ふん、同情なんぞかけるだけ無駄なんだ。こいつのせいであたいが惚れた男はみんな逃げていってしまう。やっと解放されるのに同情なんてしてやれるか」
そして女の人の言葉は今度はあたしに向かって投げ掛けられる
「あんたは、どうなんだい?いくら小さくても今、あんたがおかれてる状況くらい分かるだろ?多分…、いや、絶対に。あんたと母親が話せるのは今日が最後だ。今のうちに言いたいことはいっておけ」
まるで興味も無さそうに棒読みで話す女の人は固まってうつ向くあたしを眺める
「お母は…、お母は…あたしが邪魔だったの…?」
着物の裾を握りしめ、やっと出たそれは蚊の鳴くような声だった
「ああ、さっきも言っただろう?あたしはあんたが邪魔なんだ。だからここにも売った。要らなくなったら売るのは世の中で当然のことだろ?」
またも帰ってきた言葉はもはや母親が子供に言うものとは思えないほど酷なものだった
「はぁあ…。あんたもこんな母親のとこから抜け出せてよかったねぇ。ここに売りに来てもらえただけ幸せだね」
「……。」
はぁ、とため息をつきながら出ていくお母を静かに見つめながら少女はただ立ち尽くしている
その顔に哀しみの色は浮かんでいなく、ただひたすらに母親の出ていった暖簾を眺めている姿は女将の目から見てもたった6つの少女の姿とは思えなかった
“こいつはもしかしたら将来、太遊になるかもしれない”
「おい」
女将が呼ぶと少女は振り向く
その顔にはやはり哀しみの色はなく、白い顔を無表情にしてこちらをみていた
先程お母と話していた女の人が呆れたようにあたしたち親子をみていた
「ふん、同情なんぞかけるだけ無駄なんだ。こいつのせいであたいが惚れた男はみんな逃げていってしまう。やっと解放されるのに同情なんてしてやれるか」
そして女の人の言葉は今度はあたしに向かって投げ掛けられる
「あんたは、どうなんだい?いくら小さくても今、あんたがおかれてる状況くらい分かるだろ?多分…、いや、絶対に。あんたと母親が話せるのは今日が最後だ。今のうちに言いたいことはいっておけ」
まるで興味も無さそうに棒読みで話す女の人は固まってうつ向くあたしを眺める
「お母は…、お母は…あたしが邪魔だったの…?」
着物の裾を握りしめ、やっと出たそれは蚊の鳴くような声だった
「ああ、さっきも言っただろう?あたしはあんたが邪魔なんだ。だからここにも売った。要らなくなったら売るのは世の中で当然のことだろ?」
またも帰ってきた言葉はもはや母親が子供に言うものとは思えないほど酷なものだった
「はぁあ…。あんたもこんな母親のとこから抜け出せてよかったねぇ。ここに売りに来てもらえただけ幸せだね」
「……。」
はぁ、とため息をつきながら出ていくお母を静かに見つめながら少女はただ立ち尽くしている
その顔に哀しみの色は浮かんでいなく、ただひたすらに母親の出ていった暖簾を眺めている姿は女将の目から見てもたった6つの少女の姿とは思えなかった
“こいつはもしかしたら将来、太遊になるかもしれない”
「おい」
女将が呼ぶと少女は振り向く
その顔にはやはり哀しみの色はなく、白い顔を無表情にしてこちらをみていた