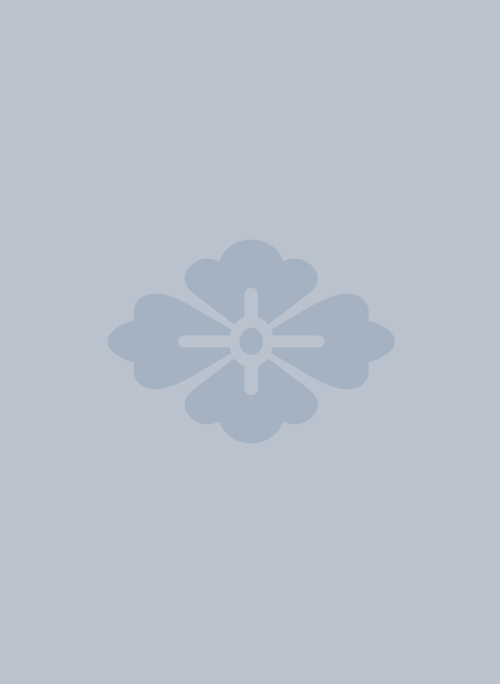睦月は吸い寄せられるように、埋まりかけているビンを掘り起こした。
真っ黒に汚れたそれは、まるで中学の時初めて拾ったビンのようだった。
蓋も硬くて開けることができない。
中に手紙が入っているかも確認できない状態だが、沖田からのものだとどこかで決め付けていた。
そして何の躊躇いもなく、ビンを岩に打ち付けた。
ガシャーンという大きな音と共に、覚悟をしていたつもりでも咄嗟に目を閉じてしまう。
ビンが砕け、太陽に反射して光を放つ。
不覚にも、綺麗だと思ってしまった。
睦月はなんとも言えない気持ちで一緒に飛び散った紙を拾い上げた。
だが、時が経ち過ぎたのか文字は薄れ、読める状態ではなかった。
だけど、睦月は微笑んで何も無い紙を上からゆっくりと目を通した。
何も伝わらない、真っ黒の紙だが、沖田の温もりが確かに感じられた気がした。
「ありがとう。沖田さん・・・」
睦月は手紙を鞄にしまい、海を後にした。