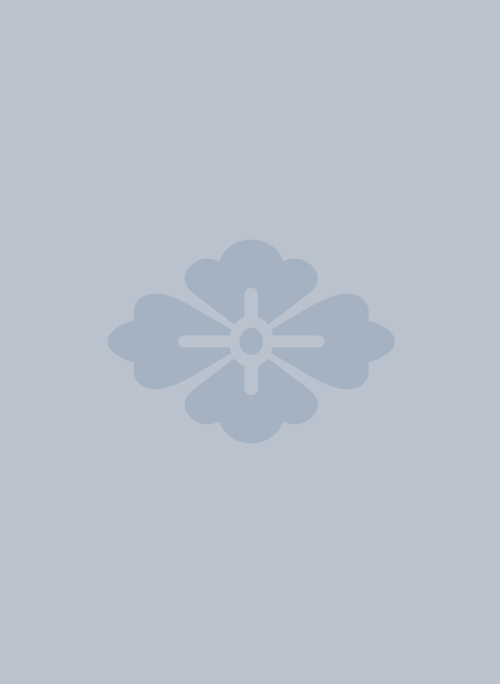――まだ幼い君は俺がいなくなって大丈夫だろうか?
――君は俺がいない間、寂しい思いをしないだろうか?
――君は…俺が死んでも………
「……けい…し…?どっか痛いんか?」
「……ごめ…っ」
――覚悟はしていた
「………ごめんな」
――していたはずなのに…
「父親らしいこと…何もできなくて……」
「……泣いとるんか?」
手拭いの冷たさとは違う、生暖かい大粒の滴が希理の額に降った。
体を痛いくらいにきつく抱きしめられているため、希理には蛍詩の顔は見えない。
しかし確実に泣いているのはわかる。
初めて蛍詩が涙を流しているところを見た希理だが、幼いながらも理由はわかっていた。