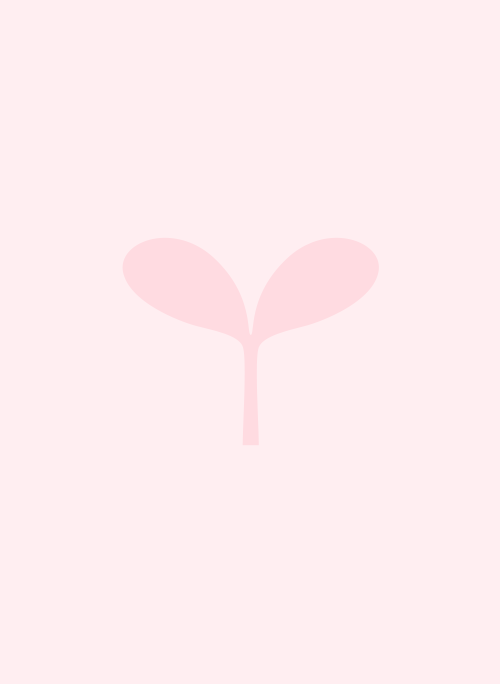「この黒猫を痛めつけたところで、魔法使いは帰ってこないと思います」
貴族の心が変わらなければ、彼はもう二度と、姿を現しはしない――。
「訳の分からないことを言う……これだから、私は庶民は嫌いなんだ」
貴族の男はそう吐き捨てて、「構ってられない」などとぶつぶつ言いながら、人込みの中を抜けて行った。
続くように、他の貴族たちも去って行く。
そんな中、一人の女性が、前へ出た。
「大丈夫?」
そう言って、彼女はリオルの頭に触れる。
石をぶつけられたところに触られれば、そこは少し腫れていて、痛みが走った。
彼女だけでなく、他の者たちもリオルに寄って行く。
それは貴族ではなく、後ろの方でいた庶民の者たちだった。