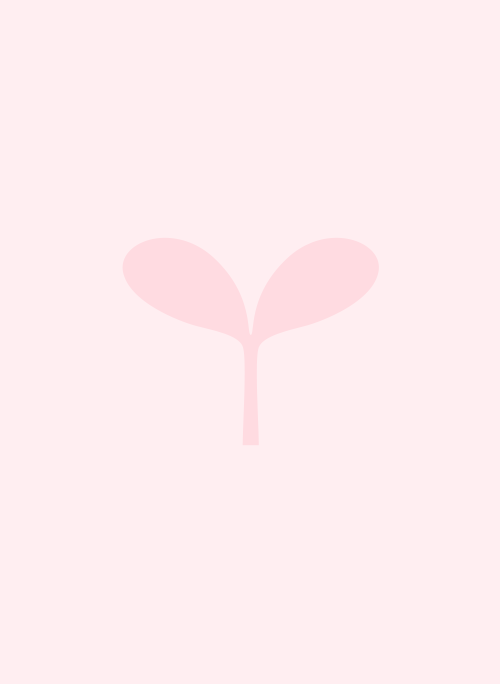いずみが朝食を終えて外へ出ると、久しぶりの蒼天が広がっていた。
ふう、と感嘆の息を吐いてから、小さく身を震わせる。朝の好天は見るだけなら爽快だったが、普段よりも冷え込みが厳しく、寒さで鼻や耳が痛くなってしまう。
まだ本格的な冬には入っていない上に、充分厚着をしているのにこの寒さ。
もう少し日が経ったらと想像するだけで、体の芯が冷えていく気がした。
早く温室に入ろうと、いずみは小走りに庭園を駆け抜けていく。
息を軽く切らしながら温室の扉を潜る頃には、早まる鼓動に合わせて体が温まっていた。
何度か深呼吸して息を整えてから、隅にある用具箱からじょうろを取り出し、中に水を汲む。
薬草たちに水を与えてから奥の植物たちにも与えていると――。
――キィィィ。扉がゆっくりと開く音がした。
「おお、やっぱり今日もここに居たか」
聞き覚えのある低い声。
まさかと思いつついずみが振り向くと、イヴァンが口元に微笑を浮かべてこちらへ近づいて来ていた。
初めてここで顔を合わせたのは数日前で、そう簡単に会うことははないと思っていたのに……。
もう怖くはなかったが、緊張して体が強ばってしまう。
いずみは息を呑み込んでから、硬くなっていた口を開いた。
「お、おはようございます、イヴァン様」
いずみのぎこちない態度にイヴァンは訝しがることはなく、「おはよう」とにこやかに答えてくれた。
「エレーナ、会えて良かったぞ。この間の花束の礼を言いたくてな……ありがとう。今までの見舞いの中で、一番母に喜んでもらえた」
勝手に温室の花を切ってしまって大丈夫だろうかと、ずっと心に引っかかっていただけに、その言葉を聞けてこちらも嬉しくなってくる。
いずみは満面の笑みを浮かべてイヴァンを見上げた。
「王妃様に少しでも喜んで頂けて光栄です。もっと上手に作れると良かったのですが……」
「あれだけ作れるなら立派なものだ。母も草花だけでよくここまで作れるものだと感心していたぞ」
イヴァンに穏やかな眼差しで見つめられ、いずみの頬に熱が集まっていく。
あまり褒められると恥ずかしくて、ここから逃げ出したくなってしまう。
視線を下に下げて、いずみが照れ隠しに指で頬を掻いていると、
「それで花束の礼をしたいのだが、何か欲しい物はあるか? あまり贅沢な物は応えられんが、出来る限りエレーナの希望に沿いたい」
イヴァンの問いかけを耳に入れた瞬間、いずみは即座に首を横に振った。
「私はイヴァン様と王妃様に喜んで頂けただけで充分です。他には何もいりません」
こちらの慌てた声に驚いたのか、イヴァンの目が丸くなり、眉間に皺を寄せて困った色を浮かべた。
「まさか、そう即答されるとは思わなかったな……エレーナ、急かさないから何が欲しいか考えてくれ。今すぐ言わずとも、また後日に言ってもらっても構わんぞ。若い娘なら、きれいな服や髪飾りとか欲しい物はたくさんあるんじゃないか?」
「いえ……あの、私は本当に何も欲しくありません。今まであまり物が欲しいと思ったことはありませんし、それに――」
ふと今までのことが頭をよぎり、急に胸の奥から痛みが突き上げてくる。
命を落とした両親や仲間たちが次々と脳裏に浮かんでは消える。
最後に残ったのは、自分を守ろうと覚悟を決めてくれた、大切な妹の顔だった。
思わず涙が込み上げそうになり、いずみはわずかに俯いて唇を噛んだ。
「――私が心から求めるものは、もう手に入れられないものばかりですから……」
ふう、と感嘆の息を吐いてから、小さく身を震わせる。朝の好天は見るだけなら爽快だったが、普段よりも冷え込みが厳しく、寒さで鼻や耳が痛くなってしまう。
まだ本格的な冬には入っていない上に、充分厚着をしているのにこの寒さ。
もう少し日が経ったらと想像するだけで、体の芯が冷えていく気がした。
早く温室に入ろうと、いずみは小走りに庭園を駆け抜けていく。
息を軽く切らしながら温室の扉を潜る頃には、早まる鼓動に合わせて体が温まっていた。
何度か深呼吸して息を整えてから、隅にある用具箱からじょうろを取り出し、中に水を汲む。
薬草たちに水を与えてから奥の植物たちにも与えていると――。
――キィィィ。扉がゆっくりと開く音がした。
「おお、やっぱり今日もここに居たか」
聞き覚えのある低い声。
まさかと思いつついずみが振り向くと、イヴァンが口元に微笑を浮かべてこちらへ近づいて来ていた。
初めてここで顔を合わせたのは数日前で、そう簡単に会うことははないと思っていたのに……。
もう怖くはなかったが、緊張して体が強ばってしまう。
いずみは息を呑み込んでから、硬くなっていた口を開いた。
「お、おはようございます、イヴァン様」
いずみのぎこちない態度にイヴァンは訝しがることはなく、「おはよう」とにこやかに答えてくれた。
「エレーナ、会えて良かったぞ。この間の花束の礼を言いたくてな……ありがとう。今までの見舞いの中で、一番母に喜んでもらえた」
勝手に温室の花を切ってしまって大丈夫だろうかと、ずっと心に引っかかっていただけに、その言葉を聞けてこちらも嬉しくなってくる。
いずみは満面の笑みを浮かべてイヴァンを見上げた。
「王妃様に少しでも喜んで頂けて光栄です。もっと上手に作れると良かったのですが……」
「あれだけ作れるなら立派なものだ。母も草花だけでよくここまで作れるものだと感心していたぞ」
イヴァンに穏やかな眼差しで見つめられ、いずみの頬に熱が集まっていく。
あまり褒められると恥ずかしくて、ここから逃げ出したくなってしまう。
視線を下に下げて、いずみが照れ隠しに指で頬を掻いていると、
「それで花束の礼をしたいのだが、何か欲しい物はあるか? あまり贅沢な物は応えられんが、出来る限りエレーナの希望に沿いたい」
イヴァンの問いかけを耳に入れた瞬間、いずみは即座に首を横に振った。
「私はイヴァン様と王妃様に喜んで頂けただけで充分です。他には何もいりません」
こちらの慌てた声に驚いたのか、イヴァンの目が丸くなり、眉間に皺を寄せて困った色を浮かべた。
「まさか、そう即答されるとは思わなかったな……エレーナ、急かさないから何が欲しいか考えてくれ。今すぐ言わずとも、また後日に言ってもらっても構わんぞ。若い娘なら、きれいな服や髪飾りとか欲しい物はたくさんあるんじゃないか?」
「いえ……あの、私は本当に何も欲しくありません。今まであまり物が欲しいと思ったことはありませんし、それに――」
ふと今までのことが頭をよぎり、急に胸の奥から痛みが突き上げてくる。
命を落とした両親や仲間たちが次々と脳裏に浮かんでは消える。
最後に残ったのは、自分を守ろうと覚悟を決めてくれた、大切な妹の顔だった。
思わず涙が込み上げそうになり、いずみはわずかに俯いて唇を噛んだ。
「――私が心から求めるものは、もう手に入れられないものばかりですから……」