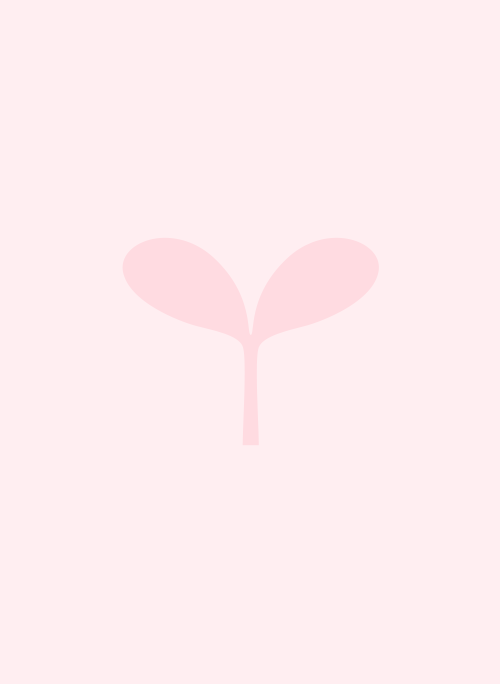「いつまでいるんだよ。」
1週間が経った頃、さすがに央が海斗に本音をぶちまけた。
ゴロゴロと畳に寝転がっている海斗の前に仁王立ちし、見下ろす。
海斗は首をひねって央を見上げた。
「あはは。」
「あはは、じゃねーって。」
ムキィッ、と地団駄を踏む央。
確かにもう熱も下がって元気なのにね。
何なんだよもぉ、と今度は崩れ落ちる。
「海斗養うためにバイトしてんじゃないんだよ、俺は。」
「うーん。」
ゴメン、と萎れた海斗に慌て、央は声を張り上げた。
「べっ、別に迷惑じゃないけど。」
ああ、もう。
優しいんだから。
「てゆーか、由宇希。」
「何?」
「お前、親心配してないのかよ。」
痛いとこ突かれた。
「ちょっとヤバい。
さすがに毎晩夕飯いらないってなると、ね。」
あたしはこの1週間、この二人と夕飯を食べていた。
夕飯を作っていくと、どうしてもね。
「海斗、この辺でアパート借りるのか?」
「いや。
……どうしようか迷ってる。」
「家、帰ったほうがいいよ。」
二人は揃ってあたしをみた。