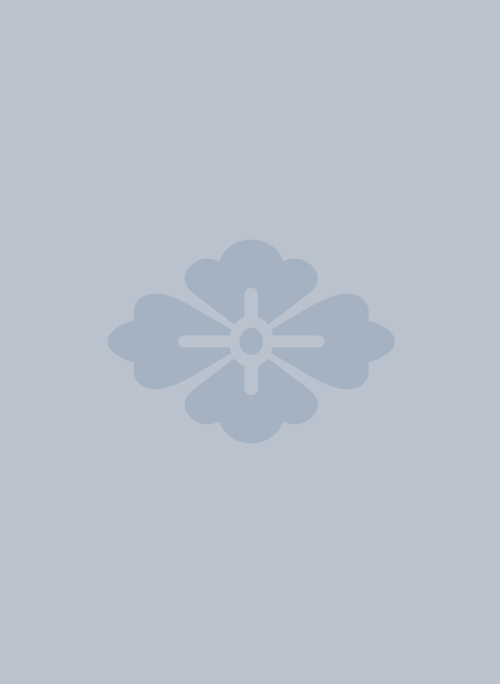「堺はさ、目が見えなくなっても私のそばにいてくれる?」
「あたりまえ。」
私は砂浜に波が打ち付けるのを眺めながら呟いた。
「変わらないでいてくれる?」
「ずっと隣にいる。」
「そっか。」
ずっと、ずっと探してた答えがもらえて、レンズ越しにぼやける海をとらえられなくなる。
涙を隠すように堺の右手と繋がれたままの左手を額にあてた。
矯正視力がこれだけ落ち、メガネ越しでも色だけはまだかすかに捉えられているこの瞳でもほとんど白杖に頼らずに外を歩けるのは堺のおかげとしかいいようがない。
今、認識できているこの海を海ととらえられるのはいつまでだろう。
いや、もしかしたらもうできていないのかもしれない。
今は波の音や潮の匂いもあるからここが海だと言えるけれど、もしそれがなかったら。
私はここがどこだか言えるのだろうか。