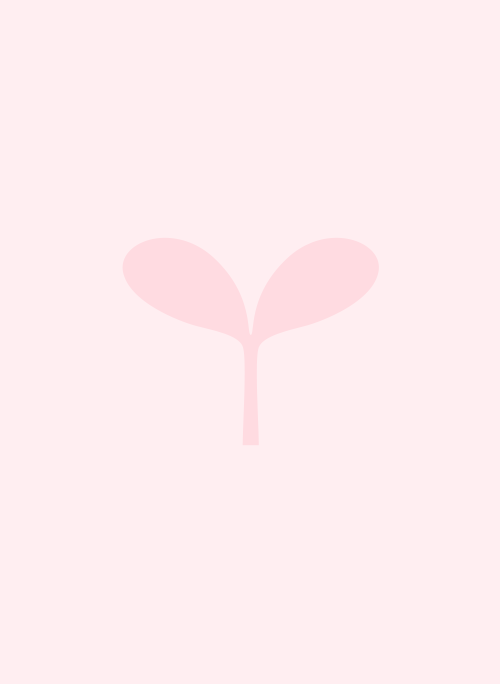「何かあったの?」
最初に話し掛けたのは、やはり珠子だった。
店にいたのは、たったひとりの僕と、珠子だけ。苦い苦い珈琲を、僕は初めてこの店に来た時のように、同じ席に座り、ゆっくりとすすっていた。
口当たりは泥そのものだった。
詳しく言い表せば、黒土を軟らかく溶かしたような泥湯を飲んでいる。ねっとりとした舌触りに、喉もとに貼り付くざらつき。
僕は、珠子のいる喫茶店に戻ってきていた。
何も話す気にもなれず、だんまりを決めこんでいた僕に、珠子も静かに珈琲を差し入れてくれた。
そして、ホットドッグ。キャベツの千切りをカレー粉で炒めた本格派だ。ケチャップの線が一本、通っている。
頬張ると涙が出そうになった。
それでも、「ありがとう」の言葉すら出なかった。
今は、何も考えたくはなかった。ただありのままの現実を受け入れる……、それが、目の前に差し出された、この珈琲を味わうことなのだ。
「今日の僕は……、まだ、お客さんだよね?」
僕はぼそりと言った。
自嘲気味に聞こえたのかもしれない。
側にいてくれた珠子は、黙ってカウンターの奥へ行ってしまった。
真っ黒な珈琲を眺めているだけで、暗い渦の底へ引き込まれて行きそうだ。
最後の一口を飲み込み、カップを皿の上に置いた。
巻き付いた指を取っ手からほどこうとした時、ふと、カップの底に目を落とした。
何やらウネウネと動いている。珈琲の染みだ。
ほんの少しカップを傾け、視線を注ぐと、底に広がっていた珈琲の模様が、みるみるうちに収縮してゆく。
僕はその動きが止まるまで、眺めた。それは、小さな溜りを作って、ようやく静止した。
テーブルに置かれた伝票の上に、お金をきっちりと積んだ。
僕はひと呼吸おいて、黙って店を出ていった。
最初に話し掛けたのは、やはり珠子だった。
店にいたのは、たったひとりの僕と、珠子だけ。苦い苦い珈琲を、僕は初めてこの店に来た時のように、同じ席に座り、ゆっくりとすすっていた。
口当たりは泥そのものだった。
詳しく言い表せば、黒土を軟らかく溶かしたような泥湯を飲んでいる。ねっとりとした舌触りに、喉もとに貼り付くざらつき。
僕は、珠子のいる喫茶店に戻ってきていた。
何も話す気にもなれず、だんまりを決めこんでいた僕に、珠子も静かに珈琲を差し入れてくれた。
そして、ホットドッグ。キャベツの千切りをカレー粉で炒めた本格派だ。ケチャップの線が一本、通っている。
頬張ると涙が出そうになった。
それでも、「ありがとう」の言葉すら出なかった。
今は、何も考えたくはなかった。ただありのままの現実を受け入れる……、それが、目の前に差し出された、この珈琲を味わうことなのだ。
「今日の僕は……、まだ、お客さんだよね?」
僕はぼそりと言った。
自嘲気味に聞こえたのかもしれない。
側にいてくれた珠子は、黙ってカウンターの奥へ行ってしまった。
真っ黒な珈琲を眺めているだけで、暗い渦の底へ引き込まれて行きそうだ。
最後の一口を飲み込み、カップを皿の上に置いた。
巻き付いた指を取っ手からほどこうとした時、ふと、カップの底に目を落とした。
何やらウネウネと動いている。珈琲の染みだ。
ほんの少しカップを傾け、視線を注ぐと、底に広がっていた珈琲の模様が、みるみるうちに収縮してゆく。
僕はその動きが止まるまで、眺めた。それは、小さな溜りを作って、ようやく静止した。
テーブルに置かれた伝票の上に、お金をきっちりと積んだ。
僕はひと呼吸おいて、黙って店を出ていった。