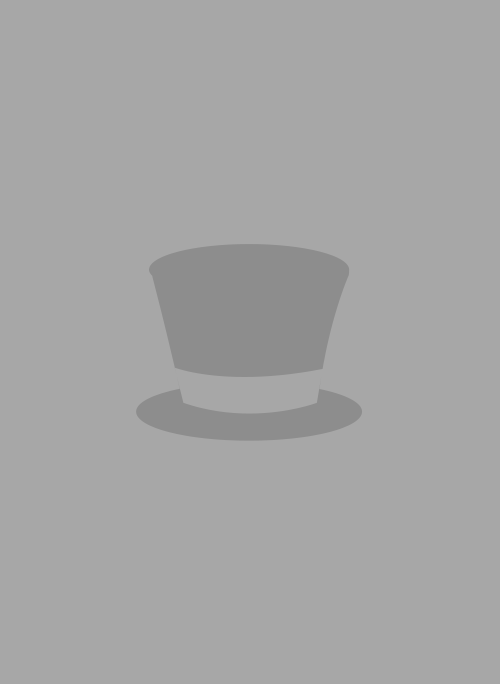私はよろけながらも、急いで扉の横にある電灯のスイッチを押した。
天井の真ん中にある2本の蛍光灯が、空気を切り裂く様な音を数回させて点灯した。
私は扉の前でゴクリと唾を飲み込むと、恐る恐るテレビ台に近付き画面を覗き込んだ――
何も無い…?
不可解な事に、ついさっきテレビの画面に書かれていた血文字が、跡形も無く消えていた。
確か今ここに…
いや、本当に書かれていたなら、今もここに何らかの痕跡があるはずだ。
ひょっとして、記憶を無くしている為に見た幻覚だろうか…
その時、不意に病室の扉が開き、張りのある大きな声が耳に飛び込んできた。
「おはよう!!
検温の時間よ」
松山さんだ。
「お、おはようございます…」
松山さんは笑顔で病室の奥まで歩いて来ると、カーテンを一気に開けた。
「早いわね。
慣れないから、余りよく眠れなかったの?」
私は白い電子体温計を手渡され、ベッドの上に寝転んだ。
あ、そうか!!
松山さんに聞いてみれば良いんだ。
もしこれからも、同じ様な事が起こり得るのならば、知っておかないと毎回怯える事になってしまう…
.