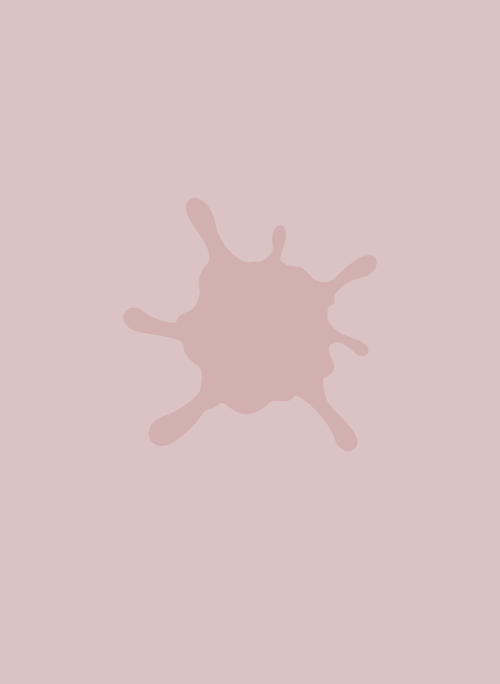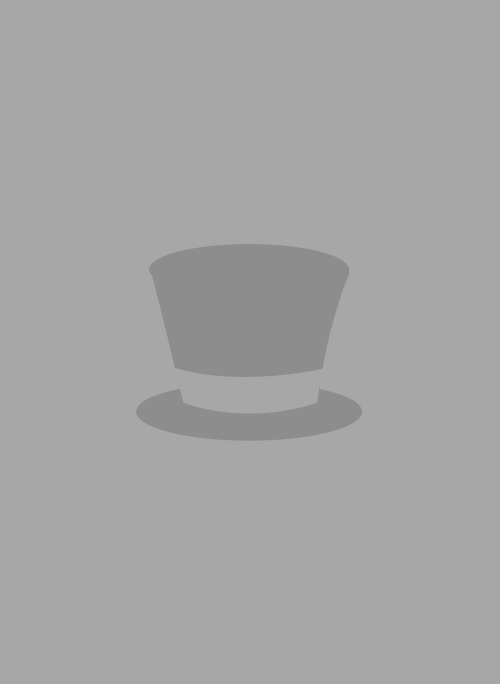しかし別れは呆気なく訪れる。
俺が十四(じゅうし)の時、彼女は呉服屋の息子に嫁いで行った。
旦那と並び幸せそうな彼女の顔――
複雑な歳頃の俺は呉服屋の息子への嫉妬も表だって出さなかった。
それでも腹の中は酷いもので。
彼女への絶望、旦那への無駄な憎悪、独り取り残された自分の喪失感――
だが恰好を付けていたい歳だった俺は、醜い本心を口にせず只無愛想に彼女らを祝福していた。
――此で何事も無ければ俺の気持ちも薄らいで行った筈なのだが、と今は思う。
俺が十四(じゅうし)の時、彼女は呉服屋の息子に嫁いで行った。
旦那と並び幸せそうな彼女の顔――
複雑な歳頃の俺は呉服屋の息子への嫉妬も表だって出さなかった。
それでも腹の中は酷いもので。
彼女への絶望、旦那への無駄な憎悪、独り取り残された自分の喪失感――
だが恰好を付けていたい歳だった俺は、醜い本心を口にせず只無愛想に彼女らを祝福していた。
――此で何事も無ければ俺の気持ちも薄らいで行った筈なのだが、と今は思う。