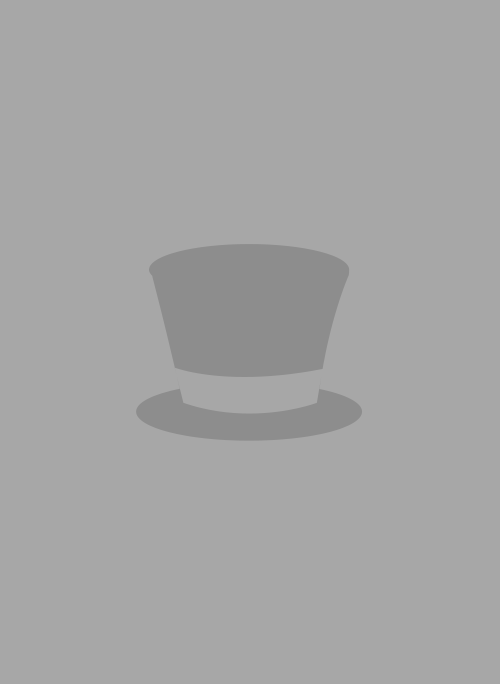彼はテーブル上のコーヒーに視線を落とした。初めて立ち寄った喫茶店、ランチは何だったのか、早くも記憶から抹消されつつある。眼前に自身の脳の萎縮が瞥見された。瞬時世界は文字通り脳の萎縮で埋め尽くされた。莫迦な、彼は白痴的微笑に唇をゆがめる。私の名において、丸丸を許さない、か。甘い、ライターの権威なんてあるのか。今時言葉なんて誰も信じない。違うじゃないか、私は別のことを夢想している。彼はコーヒーカップの中から卵形のピックを摘み上げた。恥ずかしい、高齢になってギターを持ち歩ける年齢ではない。しかし持ってきていると思えば良い。ギターとピックを結びつける、と、を現実に召喚しよう。言葉ゆえにだ。ギターは言葉に満たされた無意識から現実に気楽に引き出された。フランケンシュタインのリフを不器用に弾くと、隣の席の男が苦情を叩き付けた。
<俺は公務員だ、ここを何処だと思っている?>
<何処なんですか>
<俺が決めることだ。>
<どうぞ、ご自由に>
<何を言ってる、ところで、ブラインドタッチに慣れない入力ミス削除を排したらどうだ>
<何のお話でしょう>
<永遠についてだ>
<なるほど、青い時間は流血にストコンされる、今は昔という意味ですか<
<私の言うのはその逆の括弧のことだ>
<貴方にそんなものが見えるのですか>
<世界に在って見えないのは、私のいない世界だけだ>
<何という横暴、貴方は其処に投げ込まれているのでは?>
<俺は公務員だ、ここを何処だと思っている?>
<何処なんですか>
<俺が決めることだ。>
<どうぞ、ご自由に>
<何を言ってる、ところで、ブラインドタッチに慣れない入力ミス削除を排したらどうだ>
<何のお話でしょう>
<永遠についてだ>
<なるほど、青い時間は流血にストコンされる、今は昔という意味ですか<
<私の言うのはその逆の括弧のことだ>
<貴方にそんなものが見えるのですか>
<世界に在って見えないのは、私のいない世界だけだ>
<何という横暴、貴方は其処に投げ込まれているのでは?>