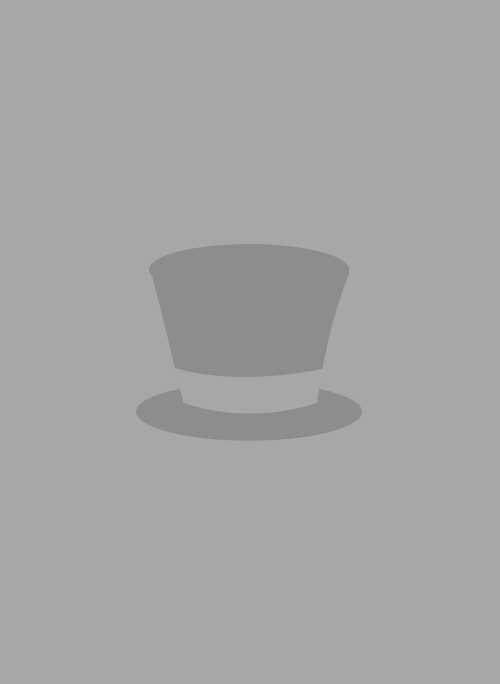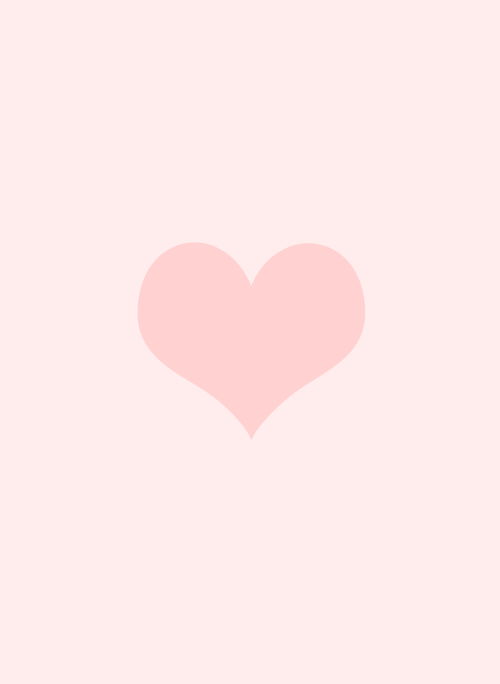「あなたが線路に落ちたとき、ある青年が助けてくれたんですよ。彼も線路に飛び込み、ホームの退避穴にあなたを引き入れてくれたんです。だからあなたは怪我一つなく助かったのですよ」
「そうだったんですか…」
あの時感じた匂い…
深空は一度目を伏せたが、再び顔をあげて、駅長の顔を見た。
「その人の連絡先、解りますか? お礼したいんですけど」
彼女がそう言うと、駅長は申し訳なさそうに首を振った。
「急いでるから、と名前も告げずに帰ってしまわれました」
「そうですか…」
彼の答えを聞いた深空は、また目を伏せる。そして残念そうに小さく溜息をついた。
「あ、そうだ」
駅長は、机の上に置かれた女性もののバッグに手を伸ばし、深空に差し出した。
「これ、あなたのですよね」
彼女はうなずきながら、手渡されたバッグの中を確認した。
「私ので間違いありません…」
内ポケットに入っている携帯電話を取り出した。幸にも、壊れた様子はなかった。中を見ると、何件か着信が入っていた。開いて詳細を確認すると、三件とも、保育園からだった。
「そうだったんですか…」
あの時感じた匂い…
深空は一度目を伏せたが、再び顔をあげて、駅長の顔を見た。
「その人の連絡先、解りますか? お礼したいんですけど」
彼女がそう言うと、駅長は申し訳なさそうに首を振った。
「急いでるから、と名前も告げずに帰ってしまわれました」
「そうですか…」
彼の答えを聞いた深空は、また目を伏せる。そして残念そうに小さく溜息をついた。
「あ、そうだ」
駅長は、机の上に置かれた女性もののバッグに手を伸ばし、深空に差し出した。
「これ、あなたのですよね」
彼女はうなずきながら、手渡されたバッグの中を確認した。
「私ので間違いありません…」
内ポケットに入っている携帯電話を取り出した。幸にも、壊れた様子はなかった。中を見ると、何件か着信が入っていた。開いて詳細を確認すると、三件とも、保育園からだった。