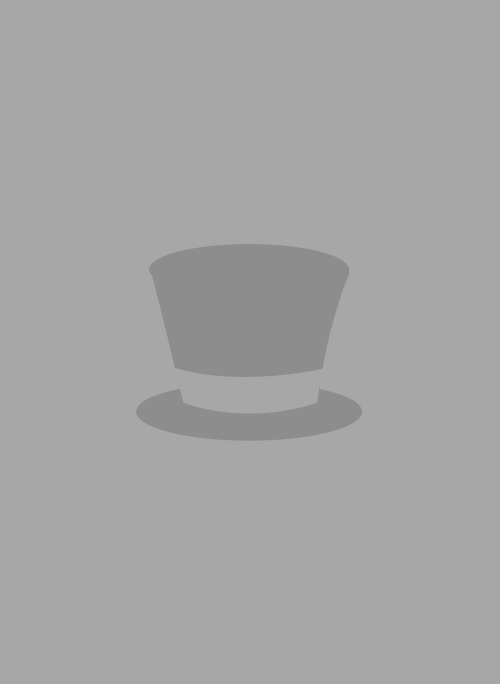移ろう季節に置いていかれそうになりながらも、深空は必死生きていた。時は経ち、3年…
風を受け、長い髪をなびかせながら歩いていると、目の前には、薄紅の花びらのシャワーが一面に舞い降りていた。太陽の光は柔らかく、暖かい。
卒業証書の入った黒い筒を手に、走り去る子供達とすれ違いながら、駅までの道程の風景を楽しんでいた。
深空の腕に掛けられている黒いハンドバッグの中には、レセプションパーティの招待状が入っている。
(…夏美、ちゃんと痩せられたかな?)
気候のせいもあり、深空は楽しそうにクスっと笑いそんなことを考えていた。
風を受け、長い髪をなびかせながら歩いていると、目の前には、薄紅の花びらのシャワーが一面に舞い降りていた。太陽の光は柔らかく、暖かい。
卒業証書の入った黒い筒を手に、走り去る子供達とすれ違いながら、駅までの道程の風景を楽しんでいた。
深空の腕に掛けられている黒いハンドバッグの中には、レセプションパーティの招待状が入っている。
(…夏美、ちゃんと痩せられたかな?)
気候のせいもあり、深空は楽しそうにクスっと笑いそんなことを考えていた。