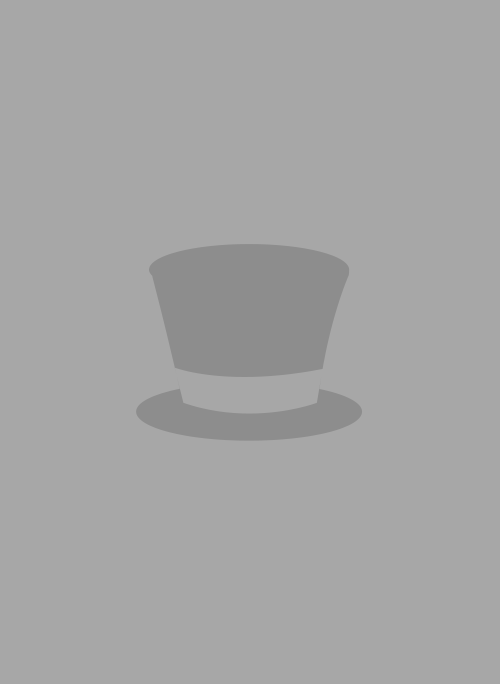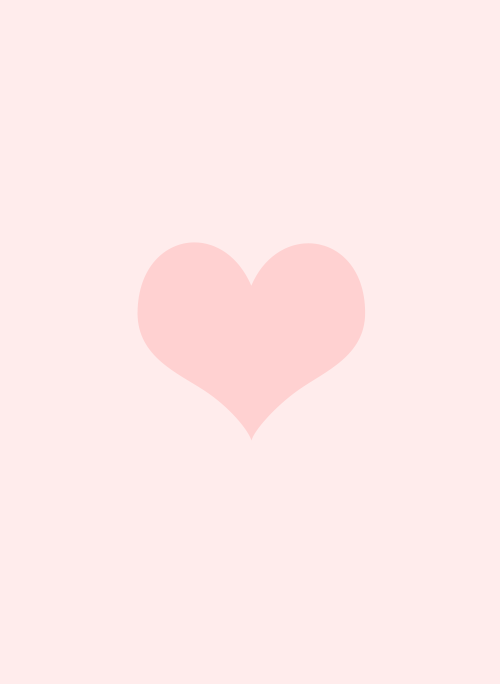「…しっかりしなさいよ。あんたが彼を包んであげなきゃ」
逸子はそう言いながら、深空の前に湯気のたった野菜スープを置いた。
辺りにはコンソメのいい香りが広がり、深空の鼻孔をくすぐった。
「いい匂い…」
その香りにつられ、深空はスプーンを握り、細かく角切りにされた野菜をすくう。そしてそれをふぅふぅしながら、口に運んだ。
「…おいし」
目の前のスープを見つめ、深空はもう一口、もう一口と、どんどん口に運んでいく。
そんな深空の様子を、逸子はキッチンに寄り掛かりながら眺めていた。その顔には、深空を見守る優しさが表れていた。
逸子はそう言いながら、深空の前に湯気のたった野菜スープを置いた。
辺りにはコンソメのいい香りが広がり、深空の鼻孔をくすぐった。
「いい匂い…」
その香りにつられ、深空はスプーンを握り、細かく角切りにされた野菜をすくう。そしてそれをふぅふぅしながら、口に運んだ。
「…おいし」
目の前のスープを見つめ、深空はもう一口、もう一口と、どんどん口に運んでいく。
そんな深空の様子を、逸子はキッチンに寄り掛かりながら眺めていた。その顔には、深空を見守る優しさが表れていた。