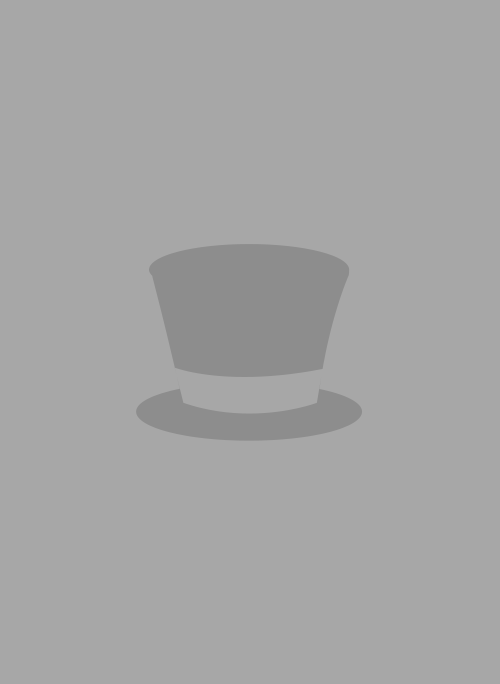「そうだ、痛い思いをさせればいいんだ」
彼はそう言いながら、辺りを見回した。
「痛い思いって、お子様はパパは本当は痛くないって言っていると……」
「本当は私も少しは痛いのですが、アイツが心配するもんだから……あ、それと……アイツがプロレスラーになるなんて言い出したから、本当はパフォーマンスで痛がっているだけだなんて教えちゃったからかな?」
「痛そうな演技をしているだけってことですか?」
「はい。すいません。あ、あの子が良い」
丁度その時、珠希が沙耶のお迎えに来たのだ。
珠希は小学生だったが、両親が忙しい時にはお迎えを頼まれるのだ。
彼は早速珠希に手招きをした。
でも珠希はその男性を見て固まっていた。
正樹の父親の超美形な顔に釘付くになってしまったのだった。
それでも彼の提案を珠希は快く引き受けた。
正樹のプロレス技に頭を痛めていたのは彼だけじゃなかったからだ。
沙耶が泣いて帰る度、珠希は正樹を懲らしめたくてしかたなかったのだ。
彼は珠希にこっそり四の字固めを教えた。
珠希は活発な女の子だったけど、そんな経験はしたことはなかった。
でも面白がって正樹に掛けたのだ。
本当は、正樹の父親の前でこんな恥ずかしい格好をしたくない。
だって足四の字固めは、両足の間に相手の足を挟んで締め上げる技だから。
それでも精一杯やったのだ。
「痛い!!」
正樹も泣き叫んだ。
でも彼は許さなかった。
「掛けてる本人は痛みは解らない。でも掛かった人は……」
「解った。痛いから早く辞めさせて」
正樹は初めてギブアップしたのだった。
正樹はその日以来、二度と沙耶にプロレスの技を掛けることはなかった。
それでも沙耶は、心に深い傷を負ったまま成長していくしかなかった。
それは何時の日にかトラウマとなっていったのだった。
彼はそう言いながら、辺りを見回した。
「痛い思いって、お子様はパパは本当は痛くないって言っていると……」
「本当は私も少しは痛いのですが、アイツが心配するもんだから……あ、それと……アイツがプロレスラーになるなんて言い出したから、本当はパフォーマンスで痛がっているだけだなんて教えちゃったからかな?」
「痛そうな演技をしているだけってことですか?」
「はい。すいません。あ、あの子が良い」
丁度その時、珠希が沙耶のお迎えに来たのだ。
珠希は小学生だったが、両親が忙しい時にはお迎えを頼まれるのだ。
彼は早速珠希に手招きをした。
でも珠希はその男性を見て固まっていた。
正樹の父親の超美形な顔に釘付くになってしまったのだった。
それでも彼の提案を珠希は快く引き受けた。
正樹のプロレス技に頭を痛めていたのは彼だけじゃなかったからだ。
沙耶が泣いて帰る度、珠希は正樹を懲らしめたくてしかたなかったのだ。
彼は珠希にこっそり四の字固めを教えた。
珠希は活発な女の子だったけど、そんな経験はしたことはなかった。
でも面白がって正樹に掛けたのだ。
本当は、正樹の父親の前でこんな恥ずかしい格好をしたくない。
だって足四の字固めは、両足の間に相手の足を挟んで締め上げる技だから。
それでも精一杯やったのだ。
「痛い!!」
正樹も泣き叫んだ。
でも彼は許さなかった。
「掛けてる本人は痛みは解らない。でも掛かった人は……」
「解った。痛いから早く辞めさせて」
正樹は初めてギブアップしたのだった。
正樹はその日以来、二度と沙耶にプロレスの技を掛けることはなかった。
それでも沙耶は、心に深い傷を負ったまま成長していくしかなかった。
それは何時の日にかトラウマとなっていったのだった。