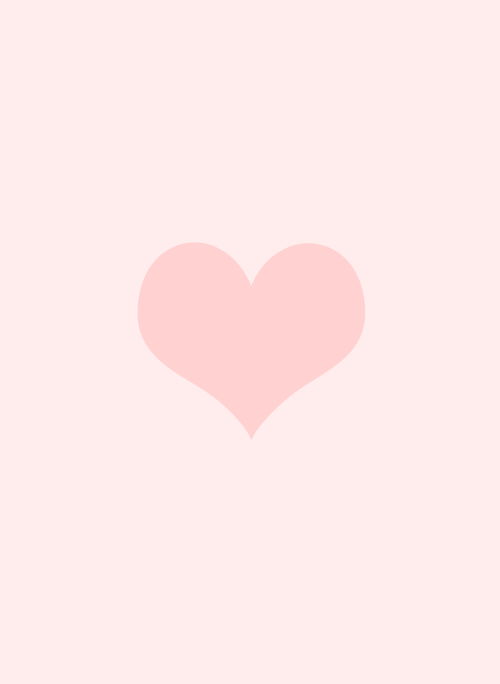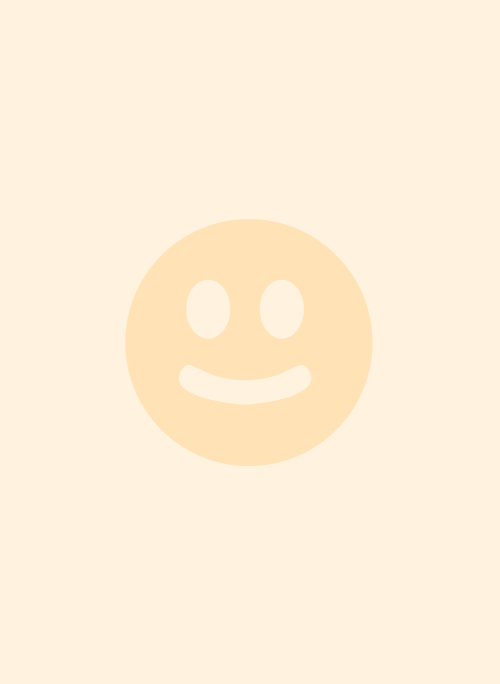「いつでも家にいるからさあ、可哀想でしょ、あの子。二人っきりになれるとこ行きなさいよ、いい加減」
私は無礼な彼女の足をよいしょ、と退けた。・・・だって龍さんがそれでいいっていうんだもーん。呟くのは心の中だけにしたんだけれど。
俺のやり方でやらせて貰う、そう宣言したけれど、龍さんはやっぱり私に合わせてくれているようだった。希望を聞いても言わないので私もそのままで過ごしているけど・・・やっぱり、問題?
元夫の時はどうだったっけな?どういう風に付き合いを濃くしていったんだっけ?つい、そう考えてしまうほどに、スローペースで清純なお付き合いをしているのだった。
考えることに少々うんざりして、私はだら~っと言った。
「行きたければ言うんじゃないの?」
それは私としては至極最もなことを言ったつもりだけれど、姉は即行でブーイングをかました。
「超スローなあんたにホテル行こうぜ~!って言うのはよっぽどの勇気が必要なのよ!可哀想に、右田君!まだ若いのに!」
「・・・私と彼は2歳しか変わらないんだけど」
「あんたが年上なんだから、ホテルや外泊くらい誘ってあげたらいいでしょうが!何なら私がプレゼントして―――――」
そのとき、ダイニングテーブルに置いた私の携帯が振動した。二人で同時に注視して、姉が嬉しそうに、おお!と言う。
「噂をすれば右田くーん!よっしゃ、潤子!今日はあんたから彼をデートに誘うのよ!」
拳を振り上げてそう主張する姉を無視して、私は立ち上がって携帯電話を取った。