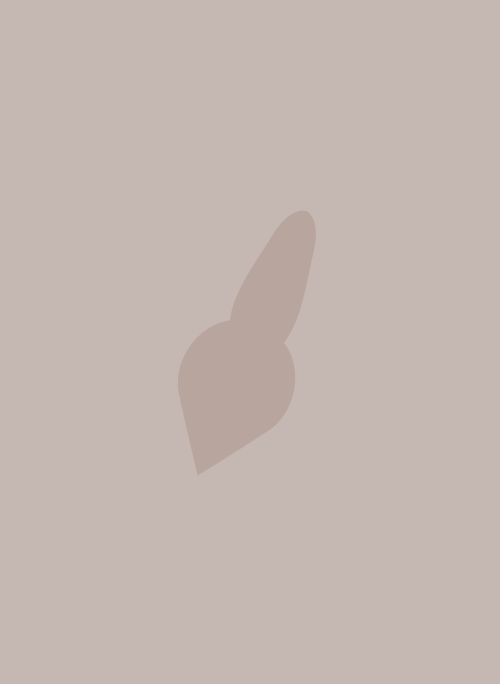「ねぇ、月夜。」
私は月夜に向き直ると、私からそっと月夜に唇を重ねた。
「どうした、急に。
もっとキスしてほしくなったのか?」
月夜だって消えるか消えないかの狭間に立っているというのに、いつも通りで
なんでこんなに怖がらずにいられるのか、私にはとうてい理解しがたい話だった。
『…希……っ』
声が遠ざかってる…これってまさか…
どうやら、私の負け…かな。
死ぬのが怖い訳じゃないけど、月夜に連れて逝ってもらえるなら…それはそれで、本望なのだ。
「…ありがとうお父さん、お母さん。
絵里、千佳ちゃん。…佑斗。そして、私に関わったすべての人たち。」
『き…』
また、みんなの声が聞こえなくなると、今度は、月夜の奥が光り始めた。
「どうやら、俺が勝っちまったみたいだな。」
「そうみたいだね。
…どんな勝負でも、月夜には適わないや。」
私は苦笑しながら、月夜に言った。