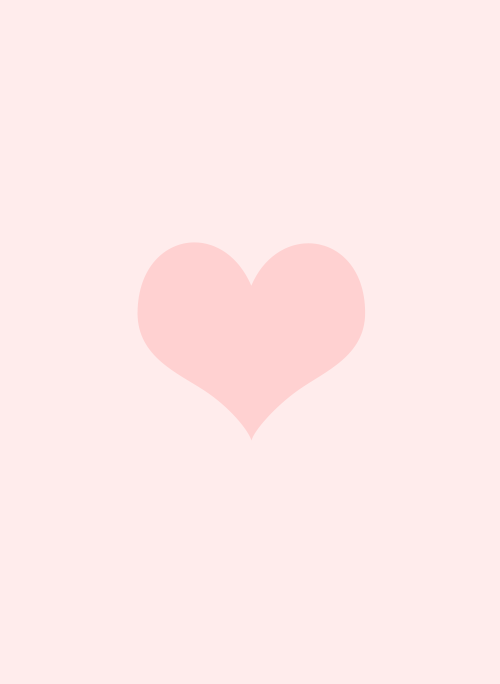放課後になって、さっきまでざわついていた教室の人気もあっという間に居なくなっていた。
いつも通りのんびりとした雰囲気で自分の席に座って文庫本を読む雨花の手には、付き合ってすぐに俺があげたブックカバーがしっかりと付けてある。
「雨花」
「憂梧くん」
俺に呼ばれて文庫本から顔を上げた雨花が、こちらを見上げて優しく微笑む。
それを見て不意に思い出すのは、昨日の別れ際にギュッと抱きついて言われた“大好き”って言葉だった。
キスした勢いでその先まで了解も得ずに進めようとした俺に、こう言ってくれたのはきっと……俺が自己嫌悪で顔を曇らせていたからだと思う。
あんなにビビって体を強張らせてた癖に……俺なら嫌じゃないって、言ってくれた雨花に今から俺が伝えること。
「俺と別れて」
やっぱり付き合ってみて合わないと思ったんだ。
なんてもっともらしいセリフを付け加えた俺の前で、一気に雨花の顔から表情が消える。
……あっ、ヤバイ。
俺、今この子を傷つけたんだ。
その顔を見た瞬間に、自分が酷いことを言ったってハッキリと自覚した。