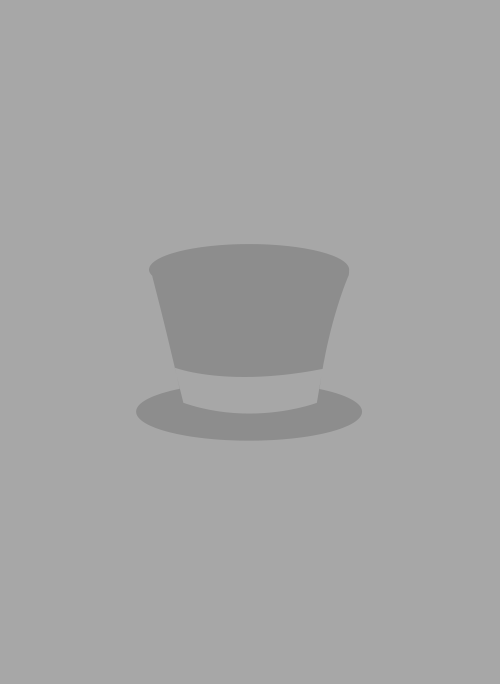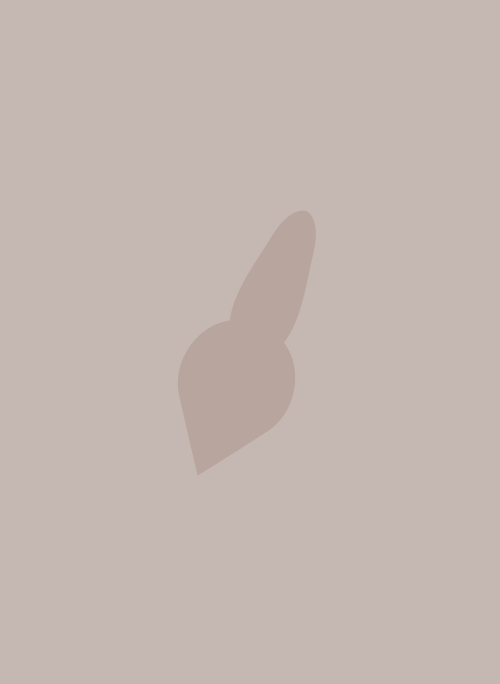特別なお得意様。
出版業界に伝でもあるのか。
「わたしはもう一冊持ってるの。だから、あげる」
「でも、……貰えないよ」
「あら、どうして? 好きなんでしょう、分島晶午」
「そうだけど……」
私の煮え切らない態度が気に入らないのか、縁は薔薇色の唇をへの字に歪めた。
「わたしからの贈り物は受け取れない?」
「そういうわけじゃないんだ。だけど、」
「もう! なんなの!?」
沸点を超えたらしい少女は、勢いよくカウンターの天板を叩いた。ティーカップの中の紅茶が波を立てる。彼女の顔を見れば、頬をぷっくり膨らませている。
「大人しく受け取りなさいよ、加賀美くんのおたんこなす!」
「おた……!?」
「要らないなら売っちゃえばいいじゃない、本屋さんでしょ!? 将来高値で売れるわ、きっと!」
「う、売らないよ!」
「なら受けとるのッ?」
「う、うん」
思わず頷いてしまった。
よくわからない理屈で捲し立てる縁の勢いに負けた。そう思うよりない。天板に載る未来の稀覯本を見つめ、私は溜め息を吐いた。