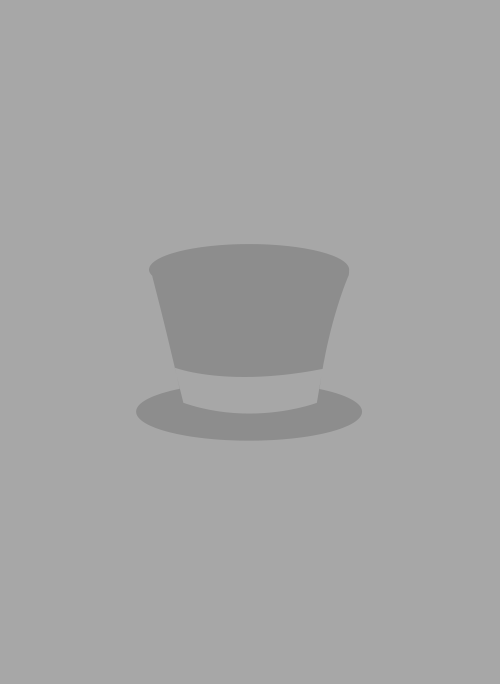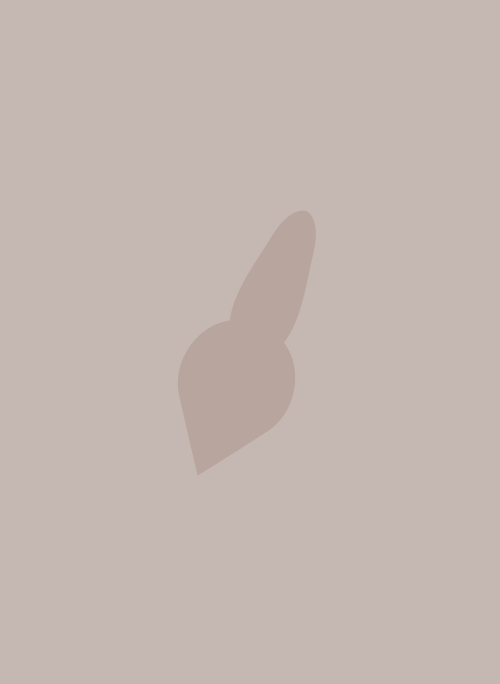縁は優雅な仕草でティーカップに口を付けた。
音もなく紅茶を吸うその姿は絵になった。映画のワンシーンだと云われたら信じてしまいそうだ。そのくらい遜色ない。
ひと口だけ紅茶を嚥下した縁は、静かにカップをソーサーに置いた。
そして、ついでに、と云いながら、膝の上の紙袋をカウンターの上に置いた。
「はい。お土産」
縁はにこやかに云って、私の目前まで紙袋をずいと滑らせる。
可愛らしいデザインのそれには、分厚いふたつ折りの茶封筒らしいものが入っていた。取り出してみると、それなりの重量がある。外観から察するに、ハードカバーの本くらいのサイズか。
縁の視線に促され、封筒の包みを開く。半分に折られていた部分を伸ばし、封を見る。封にはふたつ糸巻きが付いていた。私は糸を解き片方に巻き付けて開封する。
封筒の中に手を入れ、最初に触れたものはマットな質感のなにかだった。さらりとしたそれは、恐らく本の装丁だろう。つまり、中身の分厚いこれはハードカバーの本だ。
取り出してみると、見たことのない意匠の装丁だった。