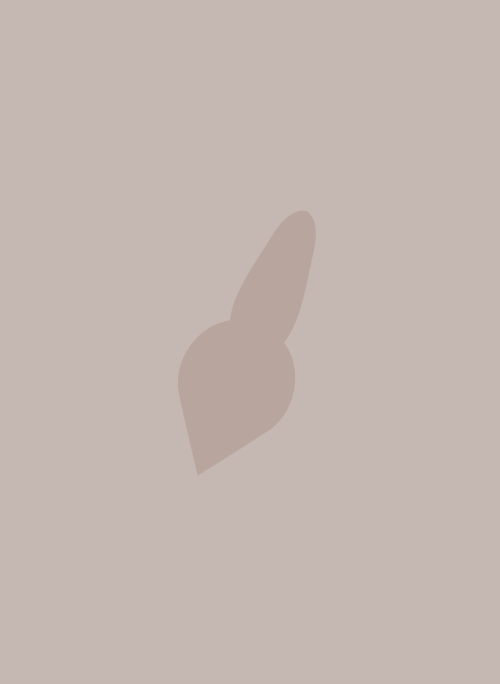背凭れに完全に身体を預けた私を、ぴんと背筋の伸びた少女が見下ろしている。その視線は、柔らかくあたたかい。
非常に個性的で、奇天烈で、そして不思議極まりないと思っていた奇矯な少女は、想像していた以上に理知的で、論理的で、そして大人だった。
外見と振る舞いと実年齢が乖離した少女が口を開く。
「ねぇ、加賀美くん」
薔薇色の唇がゆっくりと弧を描く。
「加賀美くんは、わたしの何処を好きになったの?」
「は、」
「教えてくれないの?」
少女の顔が、強かな悪女のそれに見えた。
「……そんなこと、分からないよ。気が付いたら、心に君が住み着いていたんだ」
本心だった。
「最初は変わった子だなぁ、くらいにしか思っていなかったんだ。けれど帰り際、毎回本を買っていったろう。泉鏡花に安部公房、夢野久作。どれも僕がよく読むものだった。そのときは君のことを十四、五歳くらいだろうだと思っていたから、随分面食らったよ。子どもが読む本じゃないから」