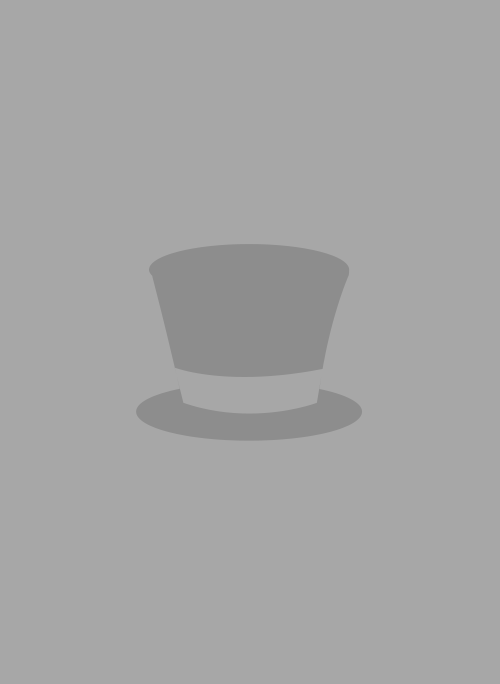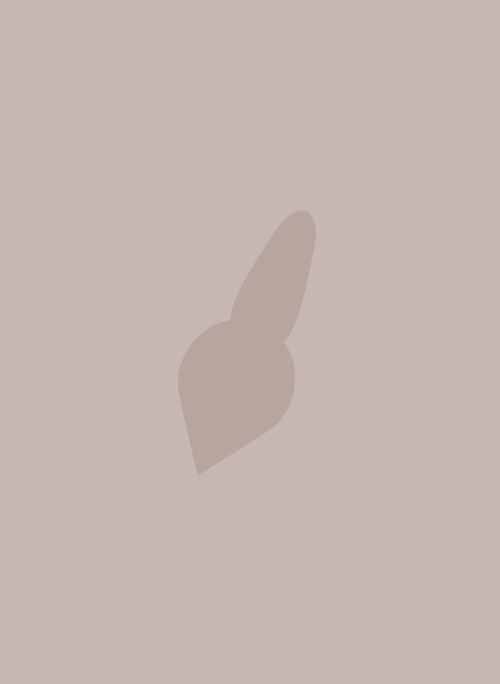「嬉しい、ありがとう!」
大袈裟に喜びを表現する縁に、私は少し戸惑った。こんなにまっすぐに感情をぶつけられたことなど経験したことがない。
縁は私の手を取り、包み込むようにしてぎゅっと握った。小さな手はひんやりとしていた。そして満面の笑みで
「わたしも好きよ、加賀美くん!」
それは突然すぎる告白だった。
一瞬にして雑音は消し飛び、少女の声だけが内耳で反響する。
「……は、」
「だって加賀美くん、好きでしょう? わたしのこと」
不思議そうに首を傾げる縁。
二の句どころかまともな言葉も出てこない。
「ふふふ。なんで分かったんだって顔。そんなの簡単だわ」
あどけない顔がぐっと大人びて、蠱惑的な雰囲気を帯びていく。
「好意を持っていない我が儘娘の戯言に付き合うほど、あなたって馬鹿じゃないでしょう?」
薔薇色をした唇が、美しく弧を描いた。
「それに、紅茶に疎いあなたがわたし好みの銘柄の茶葉を揃えたり、自分で滅多に食べない甘いお菓子をわたしが来るたびに用意したり……ちょっと考えれば分かることよ」
私の身体は、一瞬のうちに弛緩した。