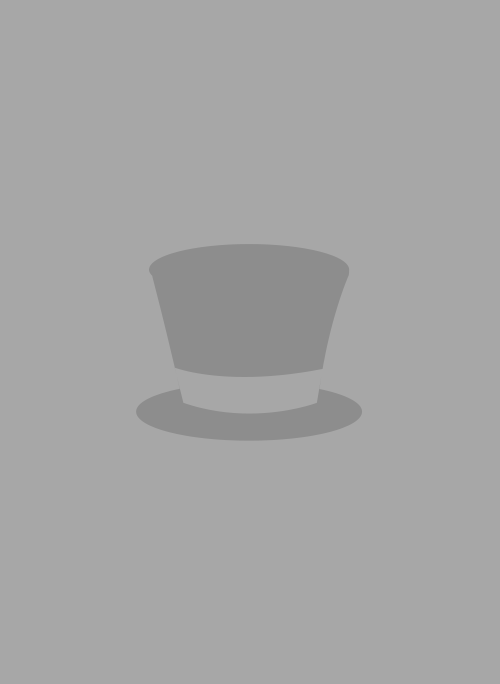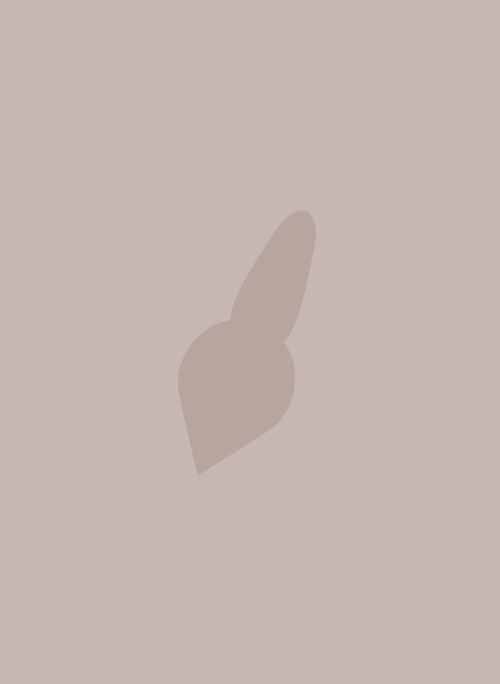「君と分島のことだけれど、結論を云うとやっぱり比べられないよ」
縁はひゅっと息を吸った。
異議を唱えようとする彼女を片手で制し、私は続ける。
「どうしてかと云うと、それは僕が人間としての分島をなにも知らないからだ。勿論君のことだって全て分かっているわけじゃないけれど、こうして面と向かって言葉を交わしている。だから君がなにか訴えるときどんな表情をしているのか分かる。でも分島はそうじゃない」
縁はじっと私の話を聞いている。
「分島が書くのは小説であって、随筆じゃない。虚構なんだ。彼がなにを思いなにを感じるのか、読者には知る術はないんだ」
努めて理論的に私は語る。
言葉を砕き、噛んで含めなければならないほど、縁は馬鹿ではない。振る舞いこそ奇矯だけれど、実はものすごく知的なのだと私は考えている。
「……と、ここまでが建前なのだけどね」
縁は少し水分の減った瞳をぱちくりさせた。
私は特に気にせず続ける。
「比べられないとは云え、君はうちのお得意様だからね。そうでなくても、君のことは嫌いじゃない」
「ほんとう!?」
嘘ではない。寧ろ、憎からず思っている。
私は本音を隠したまま頷いた。
途端に縁はぱっと顔を綻ばせた。