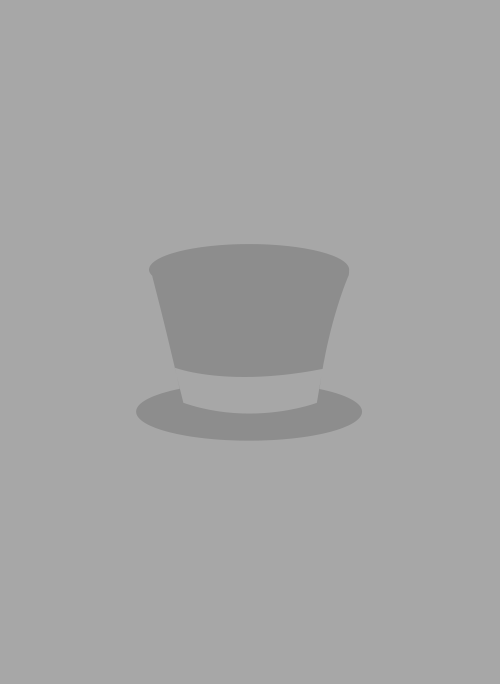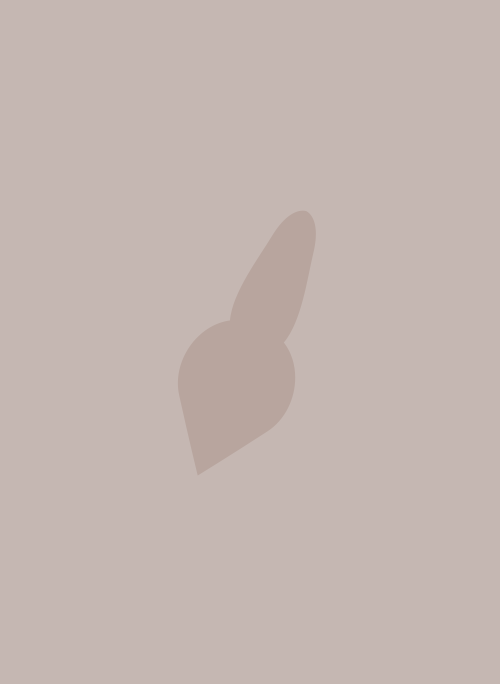なんだか居心地が悪くなり、視線を泳がせる。視界の隅では縁が、疾うに空になっているだろうティーカップに口を付け続けている。
この空気だけがざわざわとした場を取り成す言葉が見付からない。視線をうろうろさせながら、私は懸命に言葉を探した。
けれど上手い台詞は浮かばず、結局視線はカップの中に落ち着いた。微かに波打つ紅い水面には、私の凡庸な顔が映っている。
そんなとき、少女は勢いよく立ち上がった。
「加賀美くん!」
「な、なんだい」
「わたしと分島晶午、どっちが好き!?」
……。
…………。
「……はぁ?」
突然過ぎて間抜けな声しか出ない。
常々奇矯な子だとは思っていたが、この発言は予想だにしなかった。しかし目の前の少女の顔は真剣だった。縁はカウンターの上で両手を固く結んで、唇をきゅっと噛んでいる。その様子に、思わず身体が強張る。
「どっちが好きって、比べられるものじゃないだろう」
「どうしてっ?」
「だって……見知った女の子と新人作家とじゃあ分野もなにもかも違うじゃないか。同じまな板の上に載せなきゃ比べられないよ」
「むぅ……」
人形の眉間に皺が寄る。
縁は不満の二字を顔に書いたまま再び腰を下ろした。