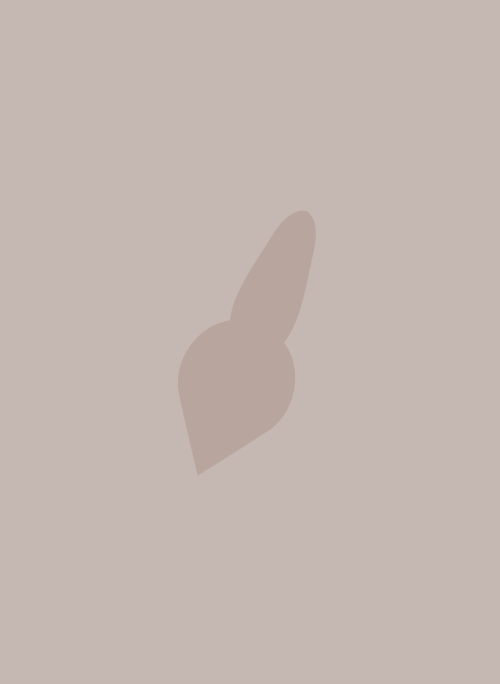「わたしはね、宮沢賢治。特に『注文の多い料理店』が好きなの。加賀美くんは?」
……。
…………。
「……は?」
「だから、好きな作家。本屋さんでしょう? ひとりくらい居ないの?」
「…………ああ、作家ね」
勘繰ってしまった自分を呪いたい。
そもそも目の前の少女は恋だの愛だの色気付いてはいないのだった。
「僕は……そうだな、最近は分島晶午をよく読むよ」
分島晶午は新進気鋭の小説家である。
二年前彗星のように文壇に現れ、デビューから一年と経たないうちに有名な賞に数作ノミネートされた。しかしその素性は一切謎に包まれている。受賞こそしていないものの、重厚な本格ミステリはうちでもよく捌けている。
分島の名前を出した途端、縁は大きな目をこれでもかと云うほどに見開き、静止した。瞬きもしない。
「縁?」
「え、あ、うん。分島晶午ね、そっか、ふぅん。……面白い?」
今の縁の様子の方が面白い、とはとても云えなかった。
「ゴシックホラーに通ずる構成が興味深いよ。書籍として流通している分は全部目を通したけど、テーマを人間の闇に絞っているのも作風によく合っているね。トリックの奇抜さに頼らないところもいい。文章も、新人とは思えないほど繊細で巧みだし、読後感は憂鬱だけれど慣れてしまえば逆に心地いいし。最新作の『モラトリアム改』は特によかった。僕は好きだよ」
素直に感想を述べると、縁はそう、と云ったっ切り黙り込んでしまった。