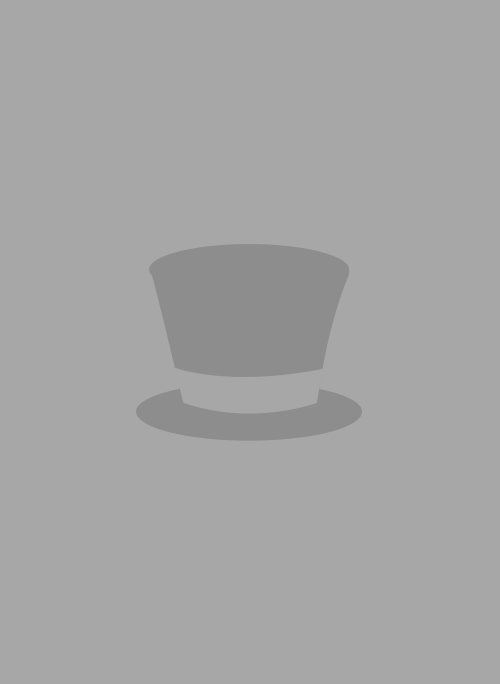囁かれる言葉の意味が分かったのだろう。亜紀の顔がカッと赤くなり、体中が熱くなるのを感じている。それでも、ここで頷いたらどうなってしまうのかは分かっているのだろう。何とかして逃げようと必死になって言葉を探している。
「で、でも……私……外泊、できない……」
「そんなこと気にしない。ちゃんと慎一さんには話してあるから。明日の夕方、ここで開かれるパーティーに間に合うように来ればいいって。そう言ってくれたよ」
亜紀が逃げ道を見つけて言葉を口にしても、惟はそれを容赦なく遮っていく。この調子では逃げ切ることはできないのではないだろうか。そんな思いが亜紀の中では大きくなっていく。
そんな中、絶え間なく降り注がれる『愛している』という言葉。その言葉が放つ甘い毒に囚われてしまったのだろうか。いつの間にか亜紀の首が微かに頷いている。
そんな彼女の反応を惟が見逃すはずもない。それまで以上に強い力で彼女を抱きしめると額にそっとキスを落としている。そのまま、今まで彼女が聞いたことのないような熱っぽい声が、耳に飛び込んでくる。
「そろそろ場所を変えようか。さすがに、これ以上のこと、ここでするのも人目があるし。亜紀も恥ずかしいでしょう?」
その声に潤んだ瞳を上げた亜紀が『惟……』と呟いている。そこに宿る表情がどこか不安気なものになっている。そのことに気がついた彼は、それこそ蕩けるような笑顔を彼女に向けていた。
「そんな顔しない。怖いことなんてしないから。全部、僕に任せておけばいいの。亜紀に最高の時間、プレゼントしてあげる。だから、心配することなんてないんだよ」
「で、でも……私……外泊、できない……」
「そんなこと気にしない。ちゃんと慎一さんには話してあるから。明日の夕方、ここで開かれるパーティーに間に合うように来ればいいって。そう言ってくれたよ」
亜紀が逃げ道を見つけて言葉を口にしても、惟はそれを容赦なく遮っていく。この調子では逃げ切ることはできないのではないだろうか。そんな思いが亜紀の中では大きくなっていく。
そんな中、絶え間なく降り注がれる『愛している』という言葉。その言葉が放つ甘い毒に囚われてしまったのだろうか。いつの間にか亜紀の首が微かに頷いている。
そんな彼女の反応を惟が見逃すはずもない。それまで以上に強い力で彼女を抱きしめると額にそっとキスを落としている。そのまま、今まで彼女が聞いたことのないような熱っぽい声が、耳に飛び込んでくる。
「そろそろ場所を変えようか。さすがに、これ以上のこと、ここでするのも人目があるし。亜紀も恥ずかしいでしょう?」
その声に潤んだ瞳を上げた亜紀が『惟……』と呟いている。そこに宿る表情がどこか不安気なものになっている。そのことに気がついた彼は、それこそ蕩けるような笑顔を彼女に向けていた。
「そんな顔しない。怖いことなんてしないから。全部、僕に任せておけばいいの。亜紀に最高の時間、プレゼントしてあげる。だから、心配することなんてないんだよ」