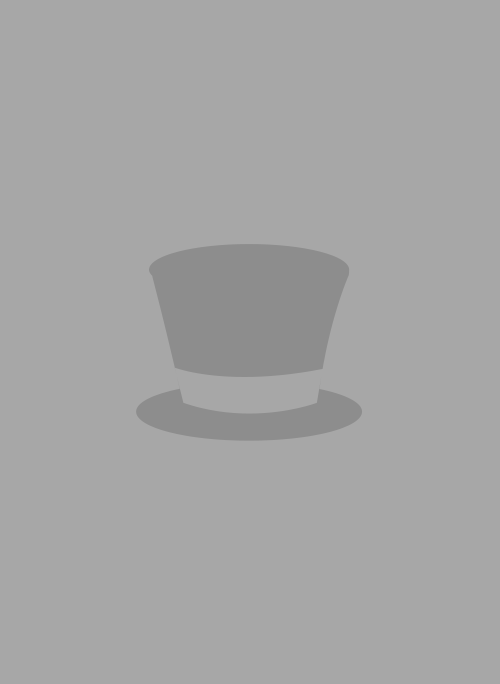そう言いながら亜紀の顔を覗き込んでくる惟。突然、至近距離に彼の顔がやってきたことで、亜紀は顔から湯気が出そうになっている。なんといっても、今の彼の姿は目の毒としか言いようがないからだ。
もともと何を着ても似合うと思っていた相手だが、白いタキシードが嫌味なほど似合っている。そして、彼のこの姿を見ると、嫌でも結婚式という言葉が頭の中をよぎっていく。
なによりも、恋に恋する女子高生の亜紀にとって、結婚式という単語は魅力的。しかし、衆人環視ともいえそうなこの状況では絶対に嫌だ。そう思う亜紀は倒れそうになるのを必死になって堪えながら、惟の言葉に頷いている。
「た、惟……分かったから……だから、ちょっと離れてよ!」
「どうして? 一番近くで君のマリエ姿見るのって、僕の当然の権利でしょう?」
「ち、近すぎるの! は、恥ずかしいんだから! みんな、見てるし、分かってよ!」
「誰も気にしてないと思うけど? でも、今は亜紀の言うこと聞いておいてあげる。それより、アンジー。ちょっと頼みたいことあるんだけど、いい?」
そう言いながら、惟は亜紀のそばをすっと離れるとアンジーに何事かを耳打ちする。彼が何を頼んでいるのかは気になるが、そばを離れてくれたのはありがたい。そう思い、大きく息を吐く亜紀にアンジーが優しく声をかけてきていた。
「亜紀ちゃん、そろそろ出番だよ。大丈夫?」
「う、うん……でも、上手く歩けるかな?」
「大丈夫。スカートの中のパニエ、遠慮なく蹴っ飛ばせばつまずかないからね。頑張って」
もともと何を着ても似合うと思っていた相手だが、白いタキシードが嫌味なほど似合っている。そして、彼のこの姿を見ると、嫌でも結婚式という言葉が頭の中をよぎっていく。
なによりも、恋に恋する女子高生の亜紀にとって、結婚式という単語は魅力的。しかし、衆人環視ともいえそうなこの状況では絶対に嫌だ。そう思う亜紀は倒れそうになるのを必死になって堪えながら、惟の言葉に頷いている。
「た、惟……分かったから……だから、ちょっと離れてよ!」
「どうして? 一番近くで君のマリエ姿見るのって、僕の当然の権利でしょう?」
「ち、近すぎるの! は、恥ずかしいんだから! みんな、見てるし、分かってよ!」
「誰も気にしてないと思うけど? でも、今は亜紀の言うこと聞いておいてあげる。それより、アンジー。ちょっと頼みたいことあるんだけど、いい?」
そう言いながら、惟は亜紀のそばをすっと離れるとアンジーに何事かを耳打ちする。彼が何を頼んでいるのかは気になるが、そばを離れてくれたのはありがたい。そう思い、大きく息を吐く亜紀にアンジーが優しく声をかけてきていた。
「亜紀ちゃん、そろそろ出番だよ。大丈夫?」
「う、うん……でも、上手く歩けるかな?」
「大丈夫。スカートの中のパニエ、遠慮なく蹴っ飛ばせばつまずかないからね。頑張って」