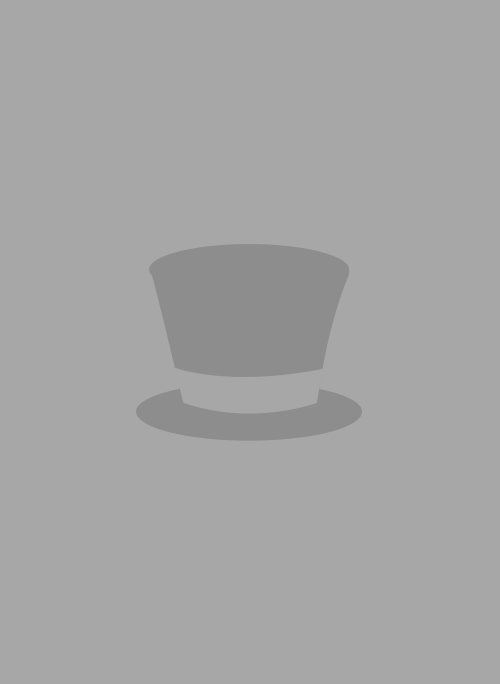「分かったよ、亜紀ちゃん。じゃあ、亜紀ちゃんだけでいいからステージに上がってよ。もうすぐ出番だし、穴あけたりしたらこのショーが台無しになっちゃうから」
「う、うん……」
アンジーの言葉に、今の現実というものが分かったのだろう。亜紀の顔が先ほどとは別の意味で赤くなる。そのままいたたまれない思いで俯いてしまう彼女の頭をアンジーは優しくポンと叩いていた。
「亜紀ちゃんの気持ちも分からないでもないから。そりゃ、惟と並んでいる姿ってみたいって思うよ。絶対に似合うと思うから。でも、亜紀ちゃんにすれば恥ずかしいっていう気持ちになるのもなんとなく分かったかな?」
そう言うと彼はクルリと後ろを振り返る。そこには白いタキシードを着た惟がどこか不機嫌です、というような表情を浮かべて立っていた。そんな彼に、アンジーが笑いながら声をかけていく。
「惟、そんな顔してもダメ。お姫様が恥ずかしいって言ってるの分かってあげないと」
「ここでそう言うの? たしかこれってアンジーも乗り気だったじゃない」
「それはそうだけどね。でも、僕としてはこのまま亜紀ちゃんに完全拒否されてショーのラストに穴をあけられる方が嫌なわけ。ついでに、そうなったら困るのは惟もでしょう?」
アンジーにそう言われると、さしもの惟もそれ以上のことは言えなくなっているようだった。それでも、どこか不満気な表情のまま、渋々といった顔で頷いている。
「アンジーの言いたいことって分かるよ。たしかに、僕も失敗はしたくないしね。分かったよ。今回は亜紀の言うこときくから。でも、今回だけだよ?」
「う、うん……」
アンジーの言葉に、今の現実というものが分かったのだろう。亜紀の顔が先ほどとは別の意味で赤くなる。そのままいたたまれない思いで俯いてしまう彼女の頭をアンジーは優しくポンと叩いていた。
「亜紀ちゃんの気持ちも分からないでもないから。そりゃ、惟と並んでいる姿ってみたいって思うよ。絶対に似合うと思うから。でも、亜紀ちゃんにすれば恥ずかしいっていう気持ちになるのもなんとなく分かったかな?」
そう言うと彼はクルリと後ろを振り返る。そこには白いタキシードを着た惟がどこか不機嫌です、というような表情を浮かべて立っていた。そんな彼に、アンジーが笑いながら声をかけていく。
「惟、そんな顔してもダメ。お姫様が恥ずかしいって言ってるの分かってあげないと」
「ここでそう言うの? たしかこれってアンジーも乗り気だったじゃない」
「それはそうだけどね。でも、僕としてはこのまま亜紀ちゃんに完全拒否されてショーのラストに穴をあけられる方が嫌なわけ。ついでに、そうなったら困るのは惟もでしょう?」
アンジーにそう言われると、さしもの惟もそれ以上のことは言えなくなっているようだった。それでも、どこか不満気な表情のまま、渋々といった顔で頷いている。
「アンジーの言いたいことって分かるよ。たしかに、僕も失敗はしたくないしね。分かったよ。今回は亜紀の言うこときくから。でも、今回だけだよ?」