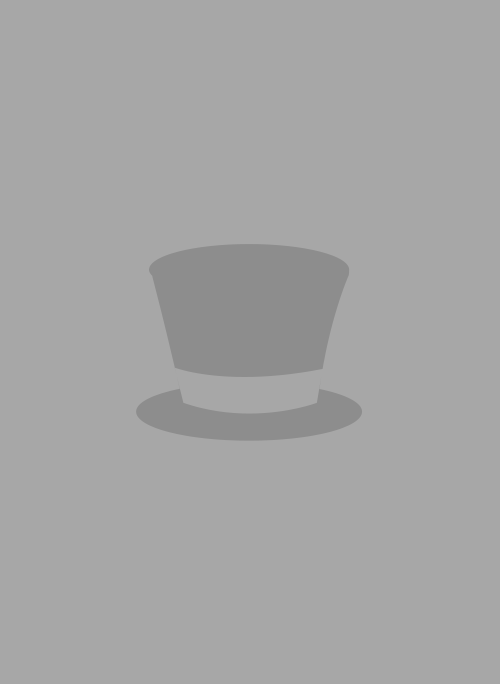そう思った時、亜紀はこの場から逃げ出したいという思いに駆られている。
このままでは、間違いなく惟が店の中に入ってくる。その時、彼が一人ならばいい。しかし、そうはならないのではないか。そんな思いが彼女の中では大きくなっていく。
その時、自分はどうするのだろう。
惟が自分以外の女性を連れているのを見て、冷静でいられるのだろうか。
いや、そんなことが我慢できるはずがない。
彼のことを好きだと自覚したのは最近のことであるのは間違いない。それでも、彼に対する思いが大きくなっていっているのも事実。
そうである以上、彼が別の女性を連れて歩いている。それだけではない。彼女だけの場所だと言っていた車の助手席にその相手を乗せている。
ということは、自分は彼の特別ではなくなったのではないか。そんな意味のない不安だけが亜紀の中で大きくなっていく。
「グラントさん! 私、惟に会いたくない!」
これが子供じみた我がままであることは分かっている。それでも、冷静になることができない。だからこそ、亜紀はアンジーに向けてそう叫ぶことしかできない。
「グラントさん、お願い! 私、ここにいたくないの!」
今の彼女はここがどこかということも分かっていないのだろう。ただ、そばにいるアンジーにすがりつくようにして叫んでいる。その声が涙交じりになっている。そのことに気がついたアンジーは思わず亜紀の体を抱き寄せていた。
このままでは、間違いなく惟が店の中に入ってくる。その時、彼が一人ならばいい。しかし、そうはならないのではないか。そんな思いが彼女の中では大きくなっていく。
その時、自分はどうするのだろう。
惟が自分以外の女性を連れているのを見て、冷静でいられるのだろうか。
いや、そんなことが我慢できるはずがない。
彼のことを好きだと自覚したのは最近のことであるのは間違いない。それでも、彼に対する思いが大きくなっていっているのも事実。
そうである以上、彼が別の女性を連れて歩いている。それだけではない。彼女だけの場所だと言っていた車の助手席にその相手を乗せている。
ということは、自分は彼の特別ではなくなったのではないか。そんな意味のない不安だけが亜紀の中で大きくなっていく。
「グラントさん! 私、惟に会いたくない!」
これが子供じみた我がままであることは分かっている。それでも、冷静になることができない。だからこそ、亜紀はアンジーに向けてそう叫ぶことしかできない。
「グラントさん、お願い! 私、ここにいたくないの!」
今の彼女はここがどこかということも分かっていないのだろう。ただ、そばにいるアンジーにすがりつくようにして叫んでいる。その声が涙交じりになっている。そのことに気がついたアンジーは思わず亜紀の体を抱き寄せていた。