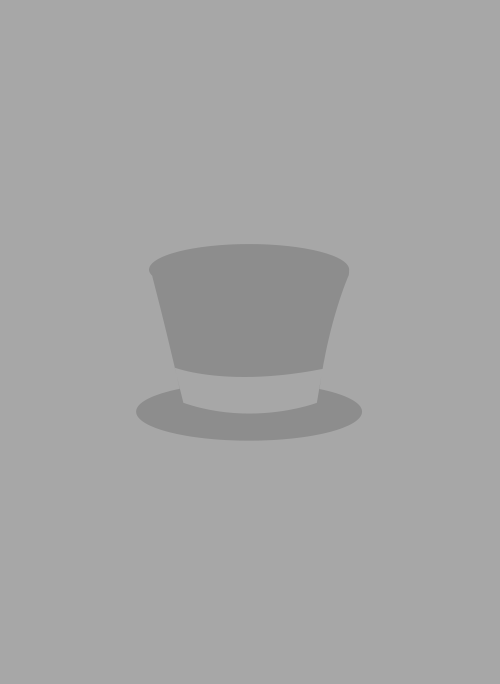しかし、そのことを千影は認められない。いや、認めたくない。それをすると、彼女のこれまでの想いの全てを否定してしまうことになるから。
だからこそ、彼女は相手が高校生ではないかとアンジーに食ってかかった。しかし、そんな彼女の抗議は見事に打ち破られている。
それどころか、彼はその女子高生のことを『自分のミューズ』とまで言ったのだ。この言葉の意味を理解した時、千影は何があっても勝てないのだ、ということを思い知らされている。だが、それでも諦めることができるはずもない。
「どうして……どうしてあんな子供が……どうして、私じゃないの? 私の方が絶対に相応しいのに……あんな子供よりも私の方が彼のこと愛しているのに……」
とっくに店の開店時間は過ぎている。本来ならば、フロアに出て接客しなければならないことは分かっている。
だが、今の状態でそれができるはずもない。そして、スタッフも事務室から漂う気配に何かを感じたのだろう。千影を呼びにくるということもしてこない。
そのことに半ば安心したように、彼女は声を殺して泣き続けることしかしていないのだった。
◇◆◇◆◇
「1週間遅くなったけど、誕生日おめでとう!」
「ありがとう、由紀子。先週は急にキャンセルしてゴメンね。ちょっと、事情があって……」
そう告げる亜紀の顔が赤くなっている。そんな友人の顔を横目で見ている由紀子。その彼女は、これだけは先に言っておこうというように、口を開いていた。
だからこそ、彼女は相手が高校生ではないかとアンジーに食ってかかった。しかし、そんな彼女の抗議は見事に打ち破られている。
それどころか、彼はその女子高生のことを『自分のミューズ』とまで言ったのだ。この言葉の意味を理解した時、千影は何があっても勝てないのだ、ということを思い知らされている。だが、それでも諦めることができるはずもない。
「どうして……どうしてあんな子供が……どうして、私じゃないの? 私の方が絶対に相応しいのに……あんな子供よりも私の方が彼のこと愛しているのに……」
とっくに店の開店時間は過ぎている。本来ならば、フロアに出て接客しなければならないことは分かっている。
だが、今の状態でそれができるはずもない。そして、スタッフも事務室から漂う気配に何かを感じたのだろう。千影を呼びにくるということもしてこない。
そのことに半ば安心したように、彼女は声を殺して泣き続けることしかしていないのだった。
◇◆◇◆◇
「1週間遅くなったけど、誕生日おめでとう!」
「ありがとう、由紀子。先週は急にキャンセルしてゴメンね。ちょっと、事情があって……」
そう告げる亜紀の顔が赤くなっている。そんな友人の顔を横目で見ている由紀子。その彼女は、これだけは先に言っておこうというように、口を開いていた。