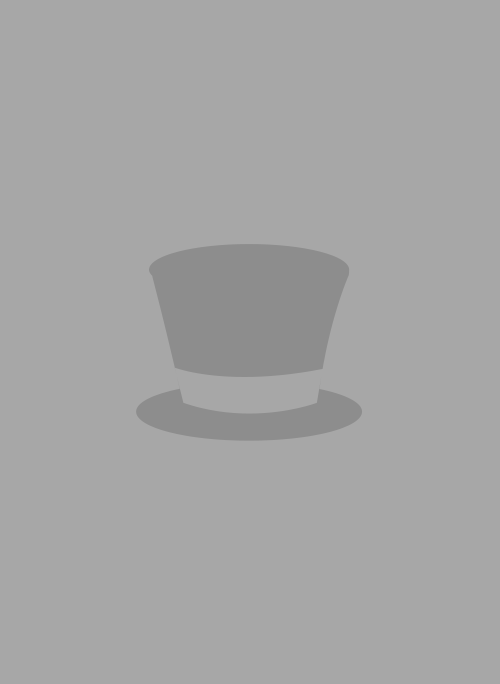千影のその声にアンジーは満足したような色をみせている。そんな彼に、どこか苛立ったような表情で千影は言葉を続けていた。
「それよりも、お訊ねしたいことがございます。どうして、このドレスをただの女子高生が着ているのですか? たしかにうちのメインユーザーが10代の女の子であることは否定しません。だからといって、アンジー様の最新作、それも一点物をこのような女の子が……」
「千影さん。それ以上言うと、惟が怒るよ。理由? 簡単だよ。彼女は惟が心底惚れ込んでいる婚約者。そして、もう一つ言っておく。彼女、一條亜紀ちゃんは僕のミューズ。だから、あのドレスは僕が亜紀ちゃんのために作った。そして、惟は婚約者にプレゼントするために僕に作らせた。この意味、分かるよね?」
アンジーのその言葉は、千影にとっては思いもよらぬものだったのだろう。彼女の顔色が髪のように蒼白となり、震える手が口元にあてられる。
「そ、そんなこと、信じられません! だって、高校生じゃありませんか! そんな子供と婚約だなんて、冗談にもほどがあります」
「千影さんは信じたくないんだ。でも、これって冗談じゃないから。だから、言葉には気をつけようね。さっきの君の言葉、惟が耳にすれば黙っていないと思うよ」
「そうはおっしゃいますが、信じられないものは信じられません。だって……」
今の千影はそれだけを口にするのが精一杯なのだろう。グッと唇を噛むと、その場から走り去っている。そんな彼女の姿を見送ったアンジーはスタッフの方を見ると『準備してね』とだけ告げている。そんな彼の姿に、声をかけられた方はコクコク頷くことしかできないようだった。
「それよりも、お訊ねしたいことがございます。どうして、このドレスをただの女子高生が着ているのですか? たしかにうちのメインユーザーが10代の女の子であることは否定しません。だからといって、アンジー様の最新作、それも一点物をこのような女の子が……」
「千影さん。それ以上言うと、惟が怒るよ。理由? 簡単だよ。彼女は惟が心底惚れ込んでいる婚約者。そして、もう一つ言っておく。彼女、一條亜紀ちゃんは僕のミューズ。だから、あのドレスは僕が亜紀ちゃんのために作った。そして、惟は婚約者にプレゼントするために僕に作らせた。この意味、分かるよね?」
アンジーのその言葉は、千影にとっては思いもよらぬものだったのだろう。彼女の顔色が髪のように蒼白となり、震える手が口元にあてられる。
「そ、そんなこと、信じられません! だって、高校生じゃありませんか! そんな子供と婚約だなんて、冗談にもほどがあります」
「千影さんは信じたくないんだ。でも、これって冗談じゃないから。だから、言葉には気をつけようね。さっきの君の言葉、惟が耳にすれば黙っていないと思うよ」
「そうはおっしゃいますが、信じられないものは信じられません。だって……」
今の千影はそれだけを口にするのが精一杯なのだろう。グッと唇を噛むと、その場から走り去っている。そんな彼女の姿を見送ったアンジーはスタッフの方を見ると『準備してね』とだけ告げている。そんな彼の姿に、声をかけられた方はコクコク頷くことしかできないようだった。