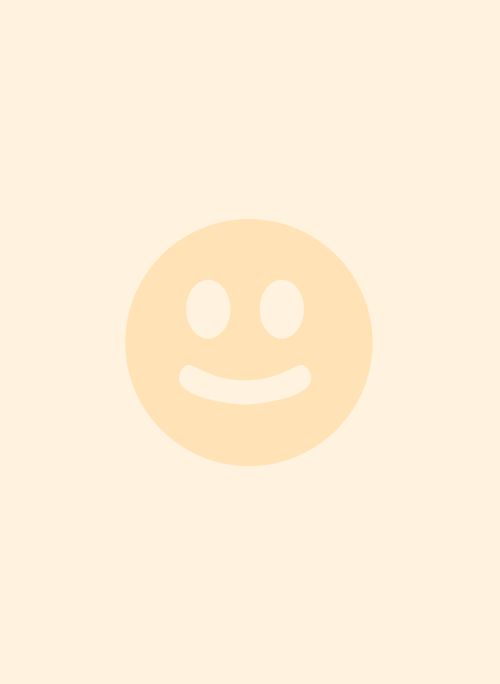「本来、『最愛』以外に興味など皆無なのだがね」
コツコツと杖をつきながら、アイヴィーはゆっくり歩を進める。
「どうしたものかね…『我々』以外に捕食者の臭いのする者が現れるとは」
「捕食者?」
眉を顰めるジャック。
「俺は捕食者なのか?」
「驚いた、君は自覚がないのだな…いや、自身が何者か知らぬ口振りだったな」
緩々と首を振り、アイヴィーは呟く。
「この都市に無駄に蔓延る家畜どもとは一線を画する…『我々』はそういう存在なのだ。僕も、君の遭遇したラミアという女も…もしかしたら君も…」
コツコツと杖をつきながら、アイヴィーはゆっくり歩を進める。
「どうしたものかね…『我々』以外に捕食者の臭いのする者が現れるとは」
「捕食者?」
眉を顰めるジャック。
「俺は捕食者なのか?」
「驚いた、君は自覚がないのだな…いや、自身が何者か知らぬ口振りだったな」
緩々と首を振り、アイヴィーは呟く。
「この都市に無駄に蔓延る家畜どもとは一線を画する…『我々』はそういう存在なのだ。僕も、君の遭遇したラミアという女も…もしかしたら君も…」