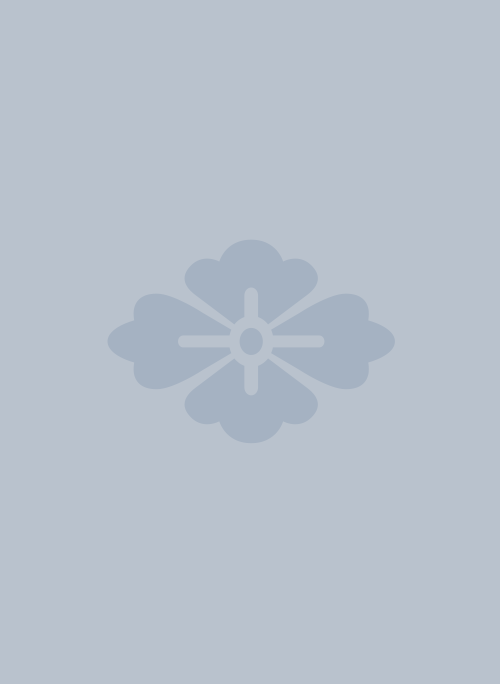随分と濡れているのがかわいそうで、どうぞ、と差し出したハンカチ。彼はそれで濡れた髪と肢体を拭いて、言ったのだった。
「とても優しい香りがする」と。
私は嬉しくて、母がラベンダーの上に広げて干してくれるのだと、得意気に話した。話は盛り上がった。もっとも、主に話していたのは私で、彼はにこにこ聞いている方が多かった。話疲れて息をついたとき、いたずらっぽく目を光らせて彼は言った。
「ねぇ、キスをしてみない?」
まるで、ちょっとあのりんごを盗ってこない?とでもいった調子で。
それからの記憶は、ひどく曖昧なものだ。静かに記憶の糸を手繰れば思い出せるのかもしれないけれど、触れるとほろほろ崩れてしまいそうなので、ずっと大事にしまってある。
それからまもなく彼は引っ越してしまって、噂に聞くこともなくなった。あの秘密の共犯者は、どんな大人になっているだろうか。
「とても優しい香りがする」と。
私は嬉しくて、母がラベンダーの上に広げて干してくれるのだと、得意気に話した。話は盛り上がった。もっとも、主に話していたのは私で、彼はにこにこ聞いている方が多かった。話疲れて息をついたとき、いたずらっぽく目を光らせて彼は言った。
「ねぇ、キスをしてみない?」
まるで、ちょっとあのりんごを盗ってこない?とでもいった調子で。
それからの記憶は、ひどく曖昧なものだ。静かに記憶の糸を手繰れば思い出せるのかもしれないけれど、触れるとほろほろ崩れてしまいそうなので、ずっと大事にしまってある。
それからまもなく彼は引っ越してしまって、噂に聞くこともなくなった。あの秘密の共犯者は、どんな大人になっているだろうか。