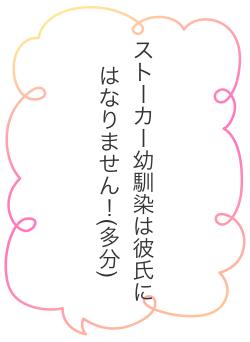「へー。ま、いいや。
自分で気づいてくんなきゃ意味ねーし。」
「なんのことー?」
「いや、いいよ。」
「そ?ならいいやー」
「あ、鍋パーティー参加するから。」
「はいよー!また今度になりそうだけど!」
「いつでも空けておくから。
…それまでに答え、出しておけよ。」
「だーかーらー!なんの答えだよー!」
「秘密。じゃーな。」
「はいはーい!お見舞いありがとねー!」
「おう。」
そう言って立ち去った葵。
「なんだったんだー?」
私は麻妃にたずねる。
「わかってんじゃんね、紅音。
好きだけどみんなと違う。
そうなったらあと残る好きは、どーゆー好きなの?」
「えー、家族愛とか?」
「他には?」
「…恋愛」
「葵は家族?」
「そうなのかもしれない!」
「…ほんとうに?」
「…違うよ。でもさ、認めたくないんだよね、
葵のこと、さ。」
「なんで?」
「だってさ、葵、私のこと女としてみて無いじゃん。
そんな恋、辛いんだもん…」
「…馬鹿だねー。
人にはぶつからなきゃ何も始まらないよ的なことを言ってたくせに、自分は逃げるんだね?」
「そーゆーわけじゃないけどさ、」
「じゃーどーゆーわけよ。」
「だってさ、こっち見てないのなんて明らかじゃん。」
「私だっておんなじよ。」
「そっか…」
「だからさ、同じ言葉返してあげるよ。
鍋パーティーで、ぶつかりな。」
「葵に?」
「もちろん。私も雅人にぶつかるからさ。」
「…慰めてね。」
「こっちだって。」
「慰めあって、カラオケ行こうね」
「鍋はどうすんのよ、」
「かきこむから!」
「熱くて無理でしょ」
「あ、そっかー」
「おばか。」
ふふふふふふ
なんて、上品な笑い方じゃなくて、
ギャハハなんて感じで笑いあった。