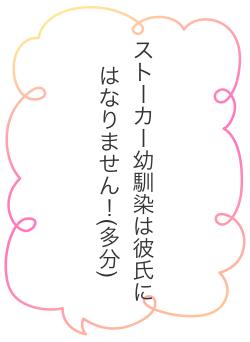「麻妃!」
私は、麻妃に声をかけた。
「…っ!あか、ねっ!」
嗚咽を紛らせながら私の名前を呼んだ、麻妃。
ただごとじゃないのはすぐにわかる。
なんで、
「なんで、泣いてるの…?」
そうたずねても、俯くだけで言葉を返してくれない。
「…私に話せないことなの?」
私は辛くなってそう言った。
苦しいよ、
大好きな親友が、
理由がわからないことで泣いてるの。
別に、泣いてるのが悪いっことじゃない。
ただ、私を頼りにしてくれないのが、苦しい。
私はいつも、麻妃にたよってばっかだから、
特に、だよ。
ねぇ、
私を、
「私を、頼ってよ…」
私は蚊の鳴くような、そんな声で言った。
「…っ!あか、あかねーっ!!、」
そう叫んで、私に抱きついてきた、麻妃。
「私ね、麻妃が泣いてる理由、わからない。
だけどさ、いつでも頼っていいの。
頼って欲しいの。
別に、話を聞かせてくれとは言わないから。
ただ、こうして、抱きついてくれて、思いっきり泣いてくれるだけでいいからさ、」
「うん、うん…っ!
ごめんね、今はまだ話せないけど、
いつかは必ず話すから…っ。」
「麻妃が話そうと思ってくれるまで、いくらでも待つから!まかせてよ!」
私は笑顔でそう言った。
麻妃も泣きながら、笑ってくれた。
笑う門には福きたる、だよ!