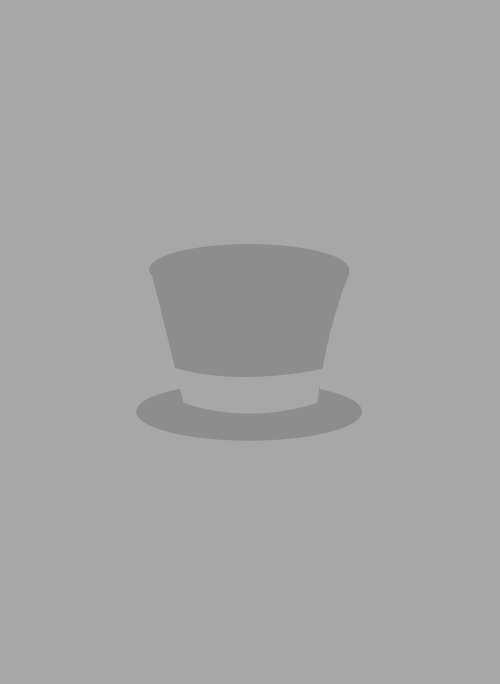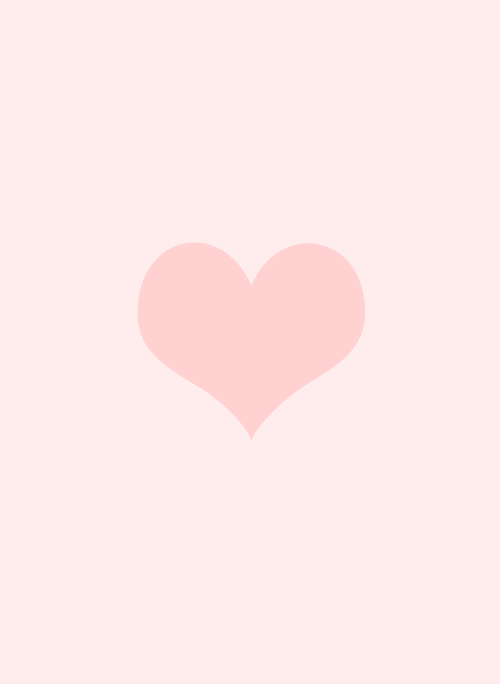雪を払い、「寒い、寒い」と口にしながらダウンジャケットを脱ぐ恭介を、私はぼーっとしながら眺めていた。
「おまたせ」
くるりと振り向き、彼はにっこりと笑顔を浮かべて私の手をぎゅっと握った。
「冷たい!」
「だって、お前がすぐにドアを開けないからだろ〜」
また少しだけ不機嫌な声で彼は言った。
「だって、こんな時間に誰かがくるなんて思わないでしょ?! 超怖かったんだよ!!」
「そっか。そうだよな。ごめん」
恭介はまたさっきの優しい笑顔で微笑むと、今度はその冷たい手で私の頬を包んだのだ。
「ちなみのほっぺ、あったかい」
「冷たいってば…」
「いいじゃん」
彼は、しばらくの間私の頬に触れていた。冷たい指先が、だんだんと暖かくなってくる。その体温を私は感じていた。
夢じゃない…
そう思うだけで、私の目の前はかすんでしまうのだ。
「おまたせ」
くるりと振り向き、彼はにっこりと笑顔を浮かべて私の手をぎゅっと握った。
「冷たい!」
「だって、お前がすぐにドアを開けないからだろ〜」
また少しだけ不機嫌な声で彼は言った。
「だって、こんな時間に誰かがくるなんて思わないでしょ?! 超怖かったんだよ!!」
「そっか。そうだよな。ごめん」
恭介はまたさっきの優しい笑顔で微笑むと、今度はその冷たい手で私の頬を包んだのだ。
「ちなみのほっぺ、あったかい」
「冷たいってば…」
「いいじゃん」
彼は、しばらくの間私の頬に触れていた。冷たい指先が、だんだんと暖かくなってくる。その体温を私は感じていた。
夢じゃない…
そう思うだけで、私の目の前はかすんでしまうのだ。