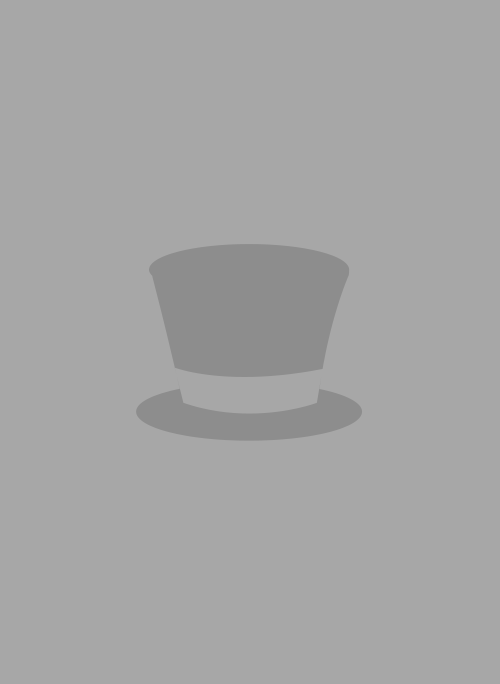あんなことがあっても、彼は私になんでも話してくれた。聞きたくないこともすべて、無邪気な子供のような目をして。
責められているのかさえ、思った時もあった。当てつけなのかとも感じた時もあった。
それでも彼はいつでも同じ笑顔を浮かべるのだ。
そうされればされるほど、あのことを許されてはいないんだと思い知らされ、私は行き場のない心を抱えていた。この先ずっとそう生きなければならいのだろう。
しかし、もうそれは高校で終わりにすると、私は決めたのだ。
もう、楽になりたい…。
私は手の甲で涙を拭くと、自分を落ち着かせるために、大きく息を吐いた。
責められているのかさえ、思った時もあった。当てつけなのかとも感じた時もあった。
それでも彼はいつでも同じ笑顔を浮かべるのだ。
そうされればされるほど、あのことを許されてはいないんだと思い知らされ、私は行き場のない心を抱えていた。この先ずっとそう生きなければならいのだろう。
しかし、もうそれは高校で終わりにすると、私は決めたのだ。
もう、楽になりたい…。
私は手の甲で涙を拭くと、自分を落ち着かせるために、大きく息を吐いた。