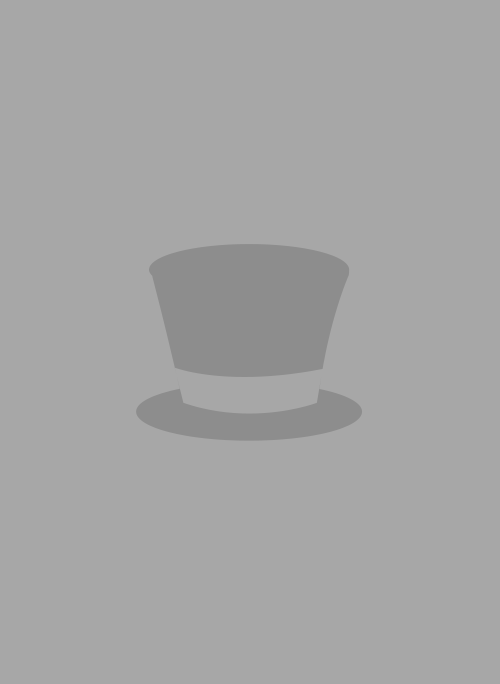「一番大事なものは、いつでもそばにあったのにな…」
寂しそうなその笑顔に、私はハッとした。それでも恭介は眉を八の字にしながら、困ったように笑っていた。
「俺たち、もっとお互いに期待しすぎたのかもしれないな。言わなくても、わかってるだろって。でもそれだとダメだって今更気付くなんて、俺たちもまだまだだな」
彼の大きな手が、私の頭を優しく包むように触れていた。
「俺はちゃんとお前の帰りをこの家で待ってるから。気を付けて行ってこいよ」
恭介は、私だけに優しくそう言ってくれた。私の肩を優しく包み、頭を撫でてくれた。そして冷たくなった私の頬に大きな手で触れた後、優しくキスをした。
「…目くらい、つむればいいのに」
いたずらに笑いながら彼がそう言うと、私は急に恥ずかしくなり、顔を赤くさせながら拳を振り上げていた。その拳をキャッチした彼は、ぎゅっと握りまた笑った。
北風が吹きすさぶ寒い朝だというのに、彼の手はとても暖かった。そして、いつの間にかこんなにも大きくなっていたことに今更ながら気付く。
「もう、この手は絶対に離さないからな! お前がどんなに遠くに行っても」
いつの間にか、私の顔にはとっくに無くしていたと思っていた笑顔が咲いていた。
寂しそうなその笑顔に、私はハッとした。それでも恭介は眉を八の字にしながら、困ったように笑っていた。
「俺たち、もっとお互いに期待しすぎたのかもしれないな。言わなくても、わかってるだろって。でもそれだとダメだって今更気付くなんて、俺たちもまだまだだな」
彼の大きな手が、私の頭を優しく包むように触れていた。
「俺はちゃんとお前の帰りをこの家で待ってるから。気を付けて行ってこいよ」
恭介は、私だけに優しくそう言ってくれた。私の肩を優しく包み、頭を撫でてくれた。そして冷たくなった私の頬に大きな手で触れた後、優しくキスをした。
「…目くらい、つむればいいのに」
いたずらに笑いながら彼がそう言うと、私は急に恥ずかしくなり、顔を赤くさせながら拳を振り上げていた。その拳をキャッチした彼は、ぎゅっと握りまた笑った。
北風が吹きすさぶ寒い朝だというのに、彼の手はとても暖かった。そして、いつの間にかこんなにも大きくなっていたことに今更ながら気付く。
「もう、この手は絶対に離さないからな! お前がどんなに遠くに行っても」
いつの間にか、私の顔にはとっくに無くしていたと思っていた笑顔が咲いていた。