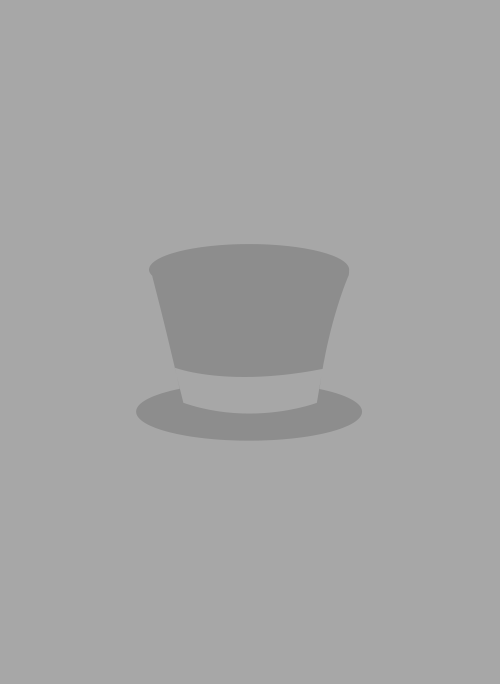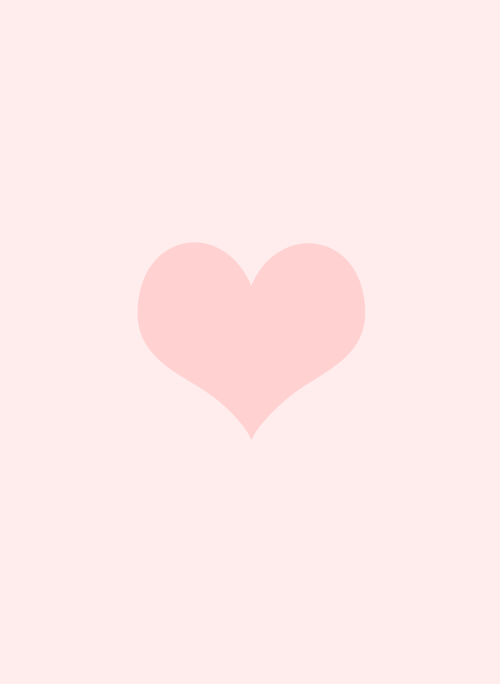もうどれくらい会ってないんだろう…?
ふと、そんなことを考えていると、今までの記憶が走馬灯のごとく、溢れ出してきたのだ。いつもその玄関のドアから明るくて優しくて、時々意地悪で、でも最後には笑ってくれる恭介の姿の幻影を…
それは純粋な彼への思いだった。
彼がいくら自分を憎もうとも、彼の目に私が映っていなくとも、私は彼のそばにいれただけで幸せだった。それは、紛れもなく事実だった。
しかし幸せだった分、苦しくて泣きなくて仕方なかったのも事実だった。自分に嘘を付くしかなかった。何もかも投げ出して、この街を出て行く覚悟を決めざるを得なかった。
ふと、そんなことを考えていると、今までの記憶が走馬灯のごとく、溢れ出してきたのだ。いつもその玄関のドアから明るくて優しくて、時々意地悪で、でも最後には笑ってくれる恭介の姿の幻影を…
それは純粋な彼への思いだった。
彼がいくら自分を憎もうとも、彼の目に私が映っていなくとも、私は彼のそばにいれただけで幸せだった。それは、紛れもなく事実だった。
しかし幸せだった分、苦しくて泣きなくて仕方なかったのも事実だった。自分に嘘を付くしかなかった。何もかも投げ出して、この街を出て行く覚悟を決めざるを得なかった。