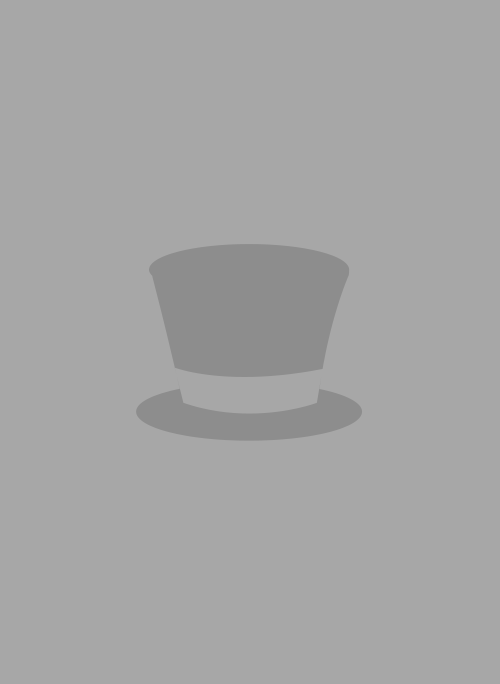私の拒絶を一身に受けて、彼の瞳はさらに大きく開き、ゆらゆらと揺れていた。私はハッと我に返り、自嘲的に笑った。
「ごめん。なんでもないの。たいしたことじゃないんだ! …忘れ物?」
手の甲で涙をぬぐいながら、私はこの場には到底似つかわしくないほどの明るい声で、彼にそう言った。
恭介は立ち上がり、「あぁ…」と答えると、さっき座っていたソファの辺りを手で探り始めた。
「携帯、忘れちゃったみたいでさ…」
探り当てた自分の携帯をパンツのポケットに収めた彼は、じっと私の顔を見つめていた。
「あ、雨、降ってきたでしょ。大丈夫だった? 愛佳との時間、感謝してよね!」
そんな彼の強い眼差しに耐えられず、私はダイニングテーブルの上を片付けながらそう言った。そして「おやすみ」と最後に残して、リビングから逃げるようにしつあ自分の部屋までかけ上がった。
「ごめん。なんでもないの。たいしたことじゃないんだ! …忘れ物?」
手の甲で涙をぬぐいながら、私はこの場には到底似つかわしくないほどの明るい声で、彼にそう言った。
恭介は立ち上がり、「あぁ…」と答えると、さっき座っていたソファの辺りを手で探り始めた。
「携帯、忘れちゃったみたいでさ…」
探り当てた自分の携帯をパンツのポケットに収めた彼は、じっと私の顔を見つめていた。
「あ、雨、降ってきたでしょ。大丈夫だった? 愛佳との時間、感謝してよね!」
そんな彼の強い眼差しに耐えられず、私はダイニングテーブルの上を片付けながらそう言った。そして「おやすみ」と最後に残して、リビングから逃げるようにしつあ自分の部屋までかけ上がった。