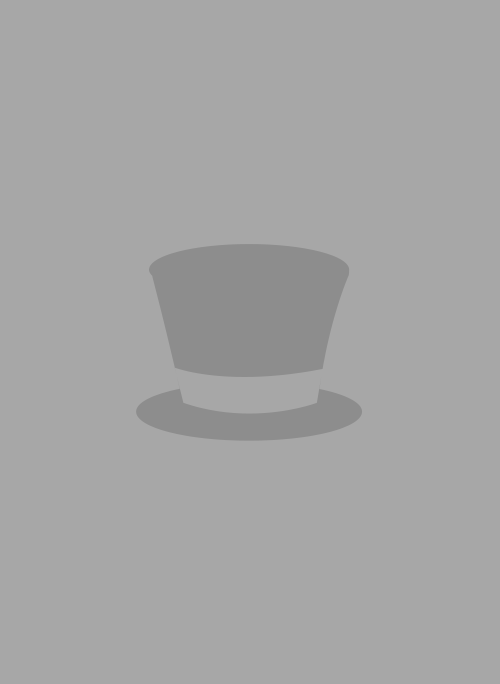今日も、いつも通りだった。
予備校の夏期講習の後、市立図書室で受験勉強をしてから家に戻ると、恭介はだらしなくソファに身を沈めてくつろいでいた。
まるで、我が家の一員のように、だ。
うちの母は、恭介が大好きだ。まるで自分の息子のように可愛がっている。娘の私より、だ。
恭介には、母親がいなかった。彼の母親は、10年ほど前、病気で亡くなったのだ。それから、恭介はよくうちにきて、恭介のお父さんが仕事の間、母に面倒を見てもらっていた。
恭介のお母さんが亡くなった時のことを、私はよく覚えている。
あれは、しとしと静かに降り続く、今日のような天気とは正反対の冬のある日だった。
恭介は、決して泣かなかった。あの時、あの雨はきっと彼の涙だと、子どもながらに私はそう思ったものだった。
予備校の夏期講習の後、市立図書室で受験勉強をしてから家に戻ると、恭介はだらしなくソファに身を沈めてくつろいでいた。
まるで、我が家の一員のように、だ。
うちの母は、恭介が大好きだ。まるで自分の息子のように可愛がっている。娘の私より、だ。
恭介には、母親がいなかった。彼の母親は、10年ほど前、病気で亡くなったのだ。それから、恭介はよくうちにきて、恭介のお父さんが仕事の間、母に面倒を見てもらっていた。
恭介のお母さんが亡くなった時のことを、私はよく覚えている。
あれは、しとしと静かに降り続く、今日のような天気とは正反対の冬のある日だった。
恭介は、決して泣かなかった。あの時、あの雨はきっと彼の涙だと、子どもながらに私はそう思ったものだった。