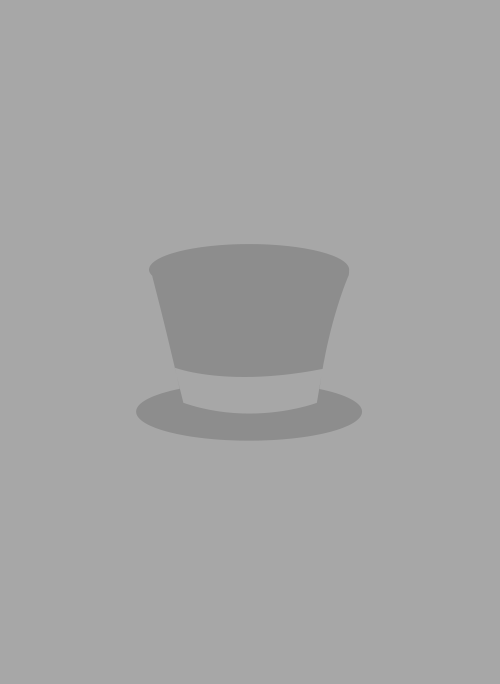誠は再び微笑みを見せると、自転車を漕ぎ出した。
「フー…」
ゆっくりとため息を吐くと、誠は決意した。
家に着くと自分の部屋に入り、日記帳を広げた。
9月15日 予想日記
俺の日記帳に紙切れを挟んだ持ち主は、俺が校門に入ると同時に「おはよう」と声を掛けてきた。
「これで、スリーに感づかれずに会えるはずや……」
学校中で起こる、何気ない場面。そこで誠は、スリーを誰だか判断する事にした。
「これなら、裏をかきようが無いはずや!」
例えスリーが、『日記の力では会うことができない』などと書いていたとしても、これなら大丈夫。後は、スリーの隙をつけばいい。
「完璧や……完璧なはずや!」
そう自分に言い聞かせる誠。しかし内心、不安でいっぱいだった。心臓の鼓動が言う事を聞いてくれない。
「フー、フー……」
深呼吸をする。その息が、震えているのがわかる。
「……何や、何や!何、ビビッてるんや!」
自分の頬をパシパシと叩いた。そのとき、携帯電話が鳴った。
プルルルル、プルルルル……
「うわ!」
その音に驚いた。サブ画面には、『麗菜』と出ていた。誠は携帯電話を手に取ると、通話ボタンを押した。
「もしもし?」
「もしもし、麗菜?何や?」
「いや、ちょっと気になった事あったんやけど」
「何や?」
「フー…」
ゆっくりとため息を吐くと、誠は決意した。
家に着くと自分の部屋に入り、日記帳を広げた。
9月15日 予想日記
俺の日記帳に紙切れを挟んだ持ち主は、俺が校門に入ると同時に「おはよう」と声を掛けてきた。
「これで、スリーに感づかれずに会えるはずや……」
学校中で起こる、何気ない場面。そこで誠は、スリーを誰だか判断する事にした。
「これなら、裏をかきようが無いはずや!」
例えスリーが、『日記の力では会うことができない』などと書いていたとしても、これなら大丈夫。後は、スリーの隙をつけばいい。
「完璧や……完璧なはずや!」
そう自分に言い聞かせる誠。しかし内心、不安でいっぱいだった。心臓の鼓動が言う事を聞いてくれない。
「フー、フー……」
深呼吸をする。その息が、震えているのがわかる。
「……何や、何や!何、ビビッてるんや!」
自分の頬をパシパシと叩いた。そのとき、携帯電話が鳴った。
プルルルル、プルルルル……
「うわ!」
その音に驚いた。サブ画面には、『麗菜』と出ていた。誠は携帯電話を手に取ると、通話ボタンを押した。
「もしもし?」
「もしもし、麗菜?何や?」
「いや、ちょっと気になった事あったんやけど」
「何や?」