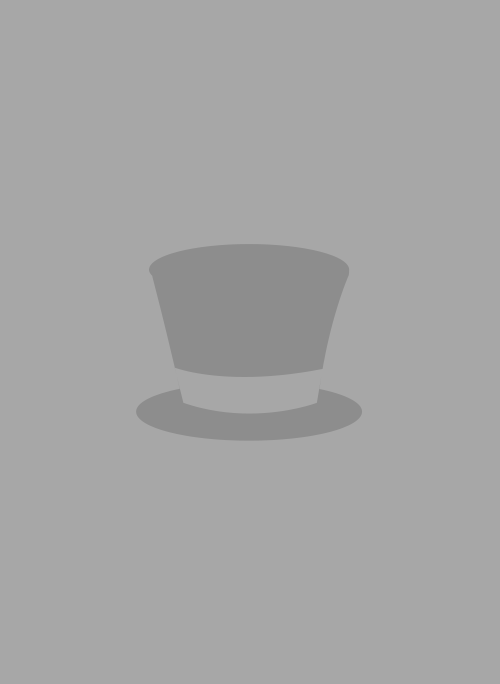「どうしたんや、誠?」
「いや、何もない…」
とりあえず誠は、一時間目が終わるを待つことにした。
一時間目、終了。
チャイムの音と同時に、誠は急いで千里の席に向かった。
「千里ちゃん…」
「何?」
無愛想な返事をする千里。
「頼む、教えてくれ。なんで、記憶があるんや」
「さぁね」
「なんで、俺に日記の事教えても何ともないんや」
「さぁね」
「頼むわ、千里ちゃん!」
「フフフ…」
千里は勝ち誇ったような不気味な笑みを浮かべた。その笑いに、苛立ちを感じ始める誠。
「もう日記が無いお前に、不思議な力があるはずない。なんでや。なんで、記憶があるんや!」
「だから、教えないって言ってんじゃん」
「くっ……」
だんだんイライラする誠。
「お前、いい加減にせぇよ」
「……」
「助けたったやろ!」
「……」
「お前なぁ…ちょっと、来い!」
誠は、黙り込む千里の腕を無理やり引っ張った。
「やめてよ、誠君!」
わざと、大声を上げる千里。そのとき、千里を引っ張る誠の腕を何者かがつかんだ。
「いや、何もない…」
とりあえず誠は、一時間目が終わるを待つことにした。
一時間目、終了。
チャイムの音と同時に、誠は急いで千里の席に向かった。
「千里ちゃん…」
「何?」
無愛想な返事をする千里。
「頼む、教えてくれ。なんで、記憶があるんや」
「さぁね」
「なんで、俺に日記の事教えても何ともないんや」
「さぁね」
「頼むわ、千里ちゃん!」
「フフフ…」
千里は勝ち誇ったような不気味な笑みを浮かべた。その笑いに、苛立ちを感じ始める誠。
「もう日記が無いお前に、不思議な力があるはずない。なんでや。なんで、記憶があるんや!」
「だから、教えないって言ってんじゃん」
「くっ……」
だんだんイライラする誠。
「お前、いい加減にせぇよ」
「……」
「助けたったやろ!」
「……」
「お前なぁ…ちょっと、来い!」
誠は、黙り込む千里の腕を無理やり引っ張った。
「やめてよ、誠君!」
わざと、大声を上げる千里。そのとき、千里を引っ張る誠の腕を何者かがつかんだ。