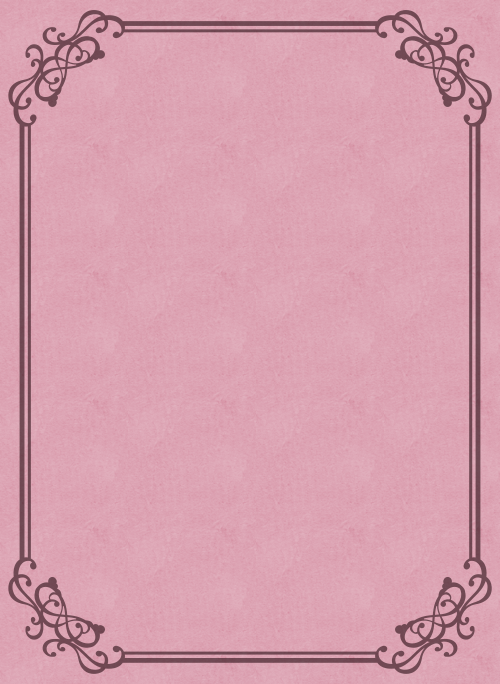「……そうだよ、それだけ」
消え入りそうな声は、雨に掻き消されていく。
「おめでと」
淡白な声だ。
私のことなんてなんとも思っていないのだ。
……そんなこと、知ってるのに。
どこかで雷の鳴る音がした。
とても遠い場所だろう、耳をくすぐる程度の、低い震えるようなその音は私の中にくすぶった気持ちに少し似ている気がした。
「……あの日、別れたのは」
雷よりもよほど地響きのように、雨は強さを増していく。
俊彦のどこか透き通った声は、雨にコーティングされてなにか神聖な言葉のようだった。
「この関係が、駄目なものだって、知ってたから」
「そうだったね」
「嫌いで、別れたんじゃない」
「うん、そうだ」
「嫌いになんて、なれない」
打ち付ける雨は、不器用な音楽だ。
様々な高低の音が、一つ壁の向こうでひしめいている。
ばたばた、ぱたぱた、ばた、ぱたたた
泣いてるみたいだと、思った。
泣いてるのは、私だった。